6.樹木の育て方
1一口メモ
(1)土に肥料を与えるときのめやす
自分より背が高い木は、胸の高さを基準にする。胸の高さの太さが10㎝のときは、
10㎝×10㎝×10㎝の入れ物に1杯入れるのが原則と考えてよい。
自分の背より小さい木は、根元の太さを基準にするとよい。例えば1㎝の太さの木は、1㎝×1㎝×1㎝の入れ物に1杯入れることになる。
株の木は、株の直径を測ってその1/10でよい。例えば1mの株の木は、10㎝×10㎝×10㎝の入れ物に1杯でよいことになる。
図
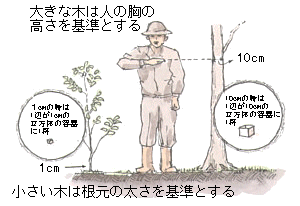 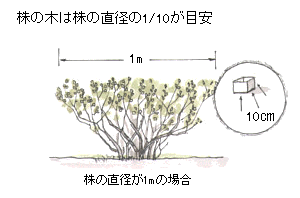 |
(2)よい苗木の条件
市販されている苗木を購入するときはよい苗木を選ばなければならない。苗木の善し悪しは根と葉と形で決まる。
よい苗の根は木が生長するために必要な水や肥料分を吸い取る役目をしているので、根が太く細い根がたくさん生えていること。葉は濃い緑色でみずみずしく、数が多いこと。幹は太く真っ直ぐであること。
図
 |
(3)木を植えるときの穴の大きさと深さ
木を植えるときは、根を大切にし根についている土はなるべく多くつけて植えるのがよい。植える穴の周囲は、根から10㎝~15㎝ほどとる。深さは、根ぎわが地平線と並ぶくらいとする。木によって例外もあるが、浅すぎても深すぎてもよくない。
図
 |
(4)ツツジ・シャクナゲの植え方
ツツジ。シャクナゲ類は、どこの庭にも何本か植えられている花木の一つである。ツツジ・シャクナゲ類の植え方のコツは浅植が原則で、地表(水平線)より少し高めに植えるようにすると根付きがよく、穴の底には大粒の火山灰を入れて水はけをよくする。
図
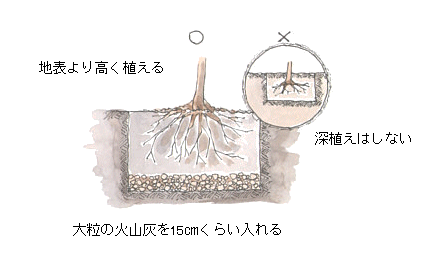 |
(5)大きな種は横にまく
大きな種(クルミ、ドングリなど)は木から落ちるとほとんど横になるので、まくときも横にしてまくとよい。
 |
(6)木を移植するときに枝を切るわけ
ある程度の大きさの木の移植の時、枝を切ることが多い。これは、自然に育っている木は地下にある根と、地上の幹、枝とのバランスがとれている。ところが、移植するときはどうしても根を切ることになり、バランスが崩れてしまう。そこで、根を切った分だけ枝を切ってバランスをとるためである。大きな木ほど根をたくさん切ることになるので、枝もたくさん切ることになる。小さな木は、根をあまり切らないので枝もそんなに切らなくても根がつく。
図
 |
(7)木の移植は春が一番よい。
小さな苗木とか少し大きくても、移植を何回もしてしっかりした根の木であれば、いつ移植してもよいが、大きな木や移植したことのない木は根がしっかり付いていないので、なるべく春5月~6月に、理想的には桜の花が咲く前に移植した方が安全である。花が開いてからだと少々不安。ですから、早く芽が開くナナカマド、シラカバ、ライラックなどはなるべく早く移植した方がよい。オンコは新しい芽が出た後でよい。
(8)ウメの枝切り
サクラとウメの枝切りは昔からよく比較対照される。サクラはあまり枝切りをしないし、ウメは長い枝をどんどん切っていいからである。
ウメは短い枝に花を咲かせ実をつけるので、短い枝を大切にする。サクラの枝を切ったときは、切り口にペンキかロウを塗っておく。そうしないと切り口から水が入って腐るからである。
(9)サクラの細い枝の処理法
サクラに細い枝がほうき状に出てきたら病気(テングス病)と考えてよい。その枝は、付け根から切るとよい。このときばかりは、あまり切らないサクラも思い切って切らないと枝が枯れてしまう。葉が落ちたときに見つけやすい。
(10)モミジの枝切り
モミジの枝切りは、葉がないときにハサミを使わないで手で折ること。ハサミで切ると、切り口から枯れるからである。少々太い枝でも手で折るようにすることが大切である。
(11)ツツジの刈り込み
ツツジは性質が強く、どんな土にもよく育ち品種も多く昔からたくさん作られている花木の一つである。
よく、花が咲かないという人がいるが、原因の一つに枝の切りすぎがある。ツツジの枝切りは間引きするように、細い枝や混んでいる枝を切る程度にするとよい。
また、夏から秋にかけて枝を切ると花が咲かない。ツツジは花が終わって1か月ほどで次の年に咲く花の芽を付け始める。だから、花の芽が付く前に刈り込むようにしなければならない。花の芽が付いてから刈り込むと、蕾を取るのと同じなので、次の年に花が咲かないのは当然である。
(12)木の枝切りの時期
木の枝を切って形を整えるとき、葉が茂っている夏場は避ける。葉が茂っているとどうしても見づらく、形を整えるのに苦労するからである。葉が完全に落ちてから枝を切るようにしてほしい。しかし、葉の落ちない常緑樹や葉が落ちない針葉樹などは、春先の方が望ましいが、いつでもよい。
(13)木の刈り込み
木の刈り込みのコツは、上を狭く下を広く刈り込んだ方がよい。これは上の方は育ちが早く、すぐ伸びるので大きく刈って狭くするのである。下の方は育ちが悪いので、育ちをよくするために広く刈るようにする。
(14)レンギョウの枝切り
レンギョウは細長く伸びた枝の先に花を付けるので、花つきが悪いのは枝の先を切っているからである。枝の先を切ってしまうと花が咲かなくなってしまう。枝を切るときは、芽を2~3残しておくと、次の年に芽が伸びて花を咲かせるので、このように切ることが次の年に咲かせるコツである。
(15)ボタンの蕾とり
ボタンの花は大きいのが普通だが、小さい花しか咲かないことがある。この原因は、蕾を取らないからである。木の大きさにもよるが、欲張らないで花を2つ位咲かせるように蕾をとってみると、割合大きな花が咲く。これは、大きな花を咲かせるための原則で、どんな花にも通用する。
(16)苗の間引き
種のまきすぎで、芽がたくさん出たときは苗の間引きをしなければならない。これは、よい苗を作るための絶対条件である。「苗を丈夫に育てるためには、思いっきり間引け」ということである。間引くのは、小さすぎるもの、大きすぎるもの、傷がついているもの、病気にかかっているものである。苗が混んでいると、風通しが悪くなり病気にかかりやすくなる。
(17)フジの花を咲かせる方法
つるばかり伸びて、さっぱり花が咲かないフジがありませんか? これは、太い根が伸びてしまったからである。秋に太い根を切ってやると花が咲くようになる。枝は、その年伸びた蔓を30㎝ほど残して切るとよい。
図
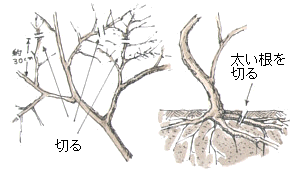 |
(18)木の根元の手入れ
不揃いの生垣や、伸びすぎた枝などは気になって切るが、木の根元から生える小枝は見落とすことが多い。切らないでおくと、木の形が変わったり枯れたりするので早めに切ることが大切である。
(19)夏に植え替えた木の手入れ
夏の暑いときの植え替えはやめた方がよい。どうしても植え替えしなければならないときは、木の根元に草を敷き、幹にはワラを巻いてやるとよい。サクラ・カイドウ・モクレンなどは木の皮が薄く幹も弱いので、寒さも防ぐ効果がある。
(20)大木になる木を育てるときの注意
木を植えるときは、その木が何年後にはどれくらいの大きさになるか、常緑樹か落葉樹かなどによって植える場所が変わる。将来の木の大きさや葉のことを考えておかないとほかの木との調和も崩れて逆効果になる。知っている木であればよいが、知らない木をうえる場合や買うときにはよく聞いておく必要がある。大きくなりすぎて家が日陰になったり、隣の家が日陰になったりして迷惑をかけることにもなりかねない。だからといって、大きすぎて切ることができなくなってしまう例もある。
野中の一軒家なら、人にも迷惑をかけないが、自分の家の北側は隣の家の南側であることに注意することが大切である。
(21)花をたくさん咲かせる方法
木によっても違うが、ほとんどの木は花が終わって1か月ほどすると花芽を付けようとする。この時期に水を控えめにしてやると、たくさんの花芽が出てたくさんの花を咲かせる。
また、徒長枝は木の生長が止まってから切るとよい。根を切ると徒長芽があまり出ず、花芽が増える。春に根を切るのも一つの方法である。
(22)花が終わってからの処理法
咲き終わった花をそのままにしておくと病虫害の原因になったり、養分を消費して木を弱らせる。終わった花はひとつひとつていねいに取り、土に埋めるか焼くかして処理するようにする。
図
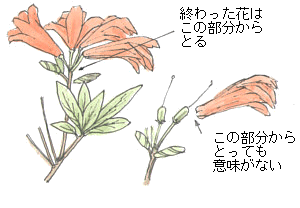 |
(23)お礼肥えとは
昔からお礼肥えという言葉がある。これは、花が終わったあとの木は大変疲れているので1日も早く回復させ、来年もいい花を咲かせるようにと入れる肥料のことである。だから、花が終わったら一日も早くお礼肥えを入れることが大切である。
肥料は、堆肥、油粕、骨粉、鶏糞などの有機質肥料がよい。
木の根元の周りを耕して柔らかくすることも効果がある。
(24)木にアリがついたとき
木にアリがつくことがあるが、こんなときは、アリの通路に木灰くずをまくか、フジターグルという薬を根元にまくと効果がある。
(25)なあるほど・一口メモ
・日なたを好む木と日かげを好む木を間違えるな。
・大きくなる木と小さい木を間違えるな
・木を植えるとき、間は広くとれ。
・木は葉が開いてから植えるな。
・木は春に植えろ。
・太い木は根回しして植えろ。
・枝を切るより葉を減らせ。
・枝は葉のないうちに切れ。
・木の管理は大切に。
・雑草は早くとれ。
・秋の枝は少し切れ。
・木にも肥料は大切、たくさんやれ。
・秋によく効く肥料はやるな。
・土は1年に1回耕せ。
・風は万病のもと。
・夏の移植は木を枯らす。
・花が咲いたら水やるな。
・シャクナゲは枝切りを嫌う。
・ツツジは水はけよい半日かげ。
・ツツジは花が終わったらすぐ枝を切れ。
・ツツジ・シャクナゲに石灰は禁物。
・バラは肥料を多くやれ。
・ボタンは春植えするな。
・シラカバは移植が難しい。
・モミジは西日を嫌う。
・ウメは太陽と仲がよい。
・実のなる木は日に当てろ。
・木の幹に苔をつけると木は弱る。
・水のかけすぎ枯れるもと。
・枝切りは芽のすぐ上から。
・深植は浅植よりもなお悪い。
・春植は活着の秘訣。
・人から聞くより自分で学べ。
・秋遅く植えるのは枯れを急ぐ。
・春伸びた枝に花がつく。
・コブシ、モクレンは9月に植えよ。けど根つきは悪い。
・病菌や虫のついた葉は焼け。
・冷たい水は毒になる。
・ピートモス、腐葉土は肥料ではない。
・買った苗木は根をすぐほどけ。
・農薬は薄めて根気よくかけろ。
・枯れ枝は害あって利なし。
・蜜植は病気と虫の巣をつくる。
・ひこばえが出たら親木は枯れる。
・夏に葉が色づいたら病気と思え。
・病害虫は駆除より予防。
・植えてすぐ肥料はやるな。
・萌芽して困るときは切り口に塩をぬれ。
・縁起の悪い気は植えるな。
・冬囲いは庭のおしゃれ。
・屋根下に木は植えるな。