(7)キンレンカ
原産地 南米ペルー
この花は、何といっても濃霧にも強風にも強く、海岸でもよく育ち、花を咲かせてくれる。したがって、標津にはぜひ欲しい花の一つである。
育て方
春の霜が降らなくなったら5月下旬〜6月上旬に花畑に直接種をまいてもいいし、少しでも早く花を咲かせようとするときは、5月上旬頃ビニールハウスか温室などで苗づくりをしてもよい。
この花は発芽もよく、気温が低くても成長する。
つる性の植物なので花畑にまくときは、30㎝程度の間隔を置いて1粒ずつまくとよい。苗づくりの場合は、発泡スチロールの箱に畑の土を入れて種をまくと、1週間ほどで芽が出る。本葉2〜3枚のときにビニールポットに移植し、本葉5〜6枚になったら花畑に植えるとよい。
この花は移植に弱いので、花の付く前に花畑に本植えすると安全である。フラワーボックスに植えてもよい花の一つである。つるが伸びるものと伸びないものの2種類があるが、どちらも丈夫な花である。
肥料が多すぎると、つるが伸び、葉が繁って花付きが悪くなる。特に窒素肥料が多いとこのようなことになるので気を付ける必要がある。追肥はしない方がよい。
半日陰程度であれば何とか育って花も付くが、日当たりのよい場所に植えた方がよい。
土は選ばないが、水はけがよいものがよい。
(8)ムギワラギク
原産地 欧州・アジア・アフリカ
花は菊の花に似ていて、花びらが堅く光って見え、触れるとバリバリ音がする。花が咲いたら、すぐに茎を切ってよく乾燥するとドライフラワーとして長く保存できる。草丈は40〜50㎝で茎が丈夫なので風で倒れることは少ない。作りやすい花の一つである。
育て方
春の霜が降らなくなったら、5月下旬頃花畑に直接まいても、発芽も生長もよい丈夫な植物である。
土はどんなものでもよく、肥料をやらなくてもよく育ち、花を咲かせてくれる。
苗づくりをして花畑に本植をしてもよいが、花畑に直接まいても花は咲くので苗づくりはしなくてもよい。花畑でたくさん芽が出たら、本葉5〜6枚のときに間引きをして移植すればよい。
枝の出が少ないので15〜20㎝程度離して植えれるとよい。種まきが遅れると、霜が降るまで花が咲かないことがあるので、5月下旬には種まきをしておきたい。
日当たりの良い場所が良く、追肥の必要はない。
花畑の花としては見栄えしないので、切り花や乾燥花にするとよい。
(9)アスター
原産地 中国・朝鮮
切り花として利用されることが多いが、花畑・鉢植えとしてもよい。花は気温が高くなり、昼が長いときに咲く長日性の花で、花色はいろいろと多い。特に最近は品種改良が進み新しい花が出回っているようである。丈夫な花なのでぜひ作って欲しい花の一つである。
育て方
暖かい地方では秋に種をまいて、初夏に花を咲かせているが、標津のような寒い地方では無理である。
5月下旬〜6月上旬頃春の霜が降らなくなってから花畑に直接まく。芽が出て本葉が5〜6枚出たら混んでいるところは間引きし15㎝〜20㎝離して栽培すると枝もよく出て花もたくさん咲く。間引きした苗は、ほかの場所に移植して育てるとよい。密生させて育てると、茎も細くなり枝も少なく、花も小さく数も少ない。
株間15〜20㎝、うね幅40〜50㎝で植えるとよい。
この花は、やせた土には育たないので、できるだけ土を肥やして育てる必要がある。したがって、堆肥をたくさん入れて耕さないといい花は望めない。
アスターは病気が多く付くので同じ畑に連作しない方がよい。場所は日当たりの良いところに栽培する。
(10)キンセンカ
原産地 地中海沿岸
切り花、花畑用として標津のような寒いところでは作りやすい花の一つである。この花は暖かい地方では秋に種をまいて次の年に花を咲かせる2年草だが、春に種をまいてもその年に花が咲くので、寒い地方では春に種をまいた方がよい。
しかし、秋にまくよりいい花は望めない。
草丈40㎝、花の大きさ5〜10㎝にもなる品種もあるが、寒い標津では大きな花は咲かない。花の色は黄色でよく目立つ。
育て方
春の霜が降らなくなった5月下旬〜6月上旬、花畑に直接まいてもよい。本葉3〜4枚になったら、混んでいるところは間引きし、30㎝位離して植える。株間が狭いとヒョロヒョロ伸びて枝もあまり出ず、花の数も少なく小さい。間引きした苗は捨てずに移植する。
土は肥えている方がよいので、元肥として堆肥を入れ、よく耕して種をまく。追肥は、間引き後本葉が5〜6枚になったころ(1週間程度)、油粕、骨粉、配合肥料などを1本の花に1/3握りほど入れてやる。窒素肥料(油粕・鶏糞など)が多すぎると草丈は伸びるが、弱々しく育ち、いい花は咲かない。
また、この花は酸性の土を嫌うので、石灰(炭カルでよい)を畑にまいてから耕した方がよい。
石灰を入れて耕してすぐに種をまくと、芽の出が悪いので、耕してから10日程おいてから種をまくようにする。
秋に種が落ちて冬を越し、次の年の春に芽が出て花をさかせることがあるので、そのまま育てると立派な花を咲かせてくれる。
丈夫な作りやすい花で、寒さに強いので標津に向く花の一つ。ぜひ作りたい花の一つである。
風に弱く、よく倒れる欠点がある。
図
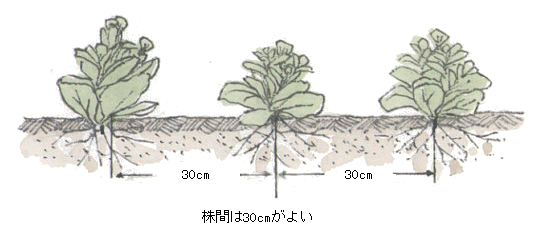 |
(11)キンギョソウ
原産地 地中海沿岸
花畑・プランター・鉢植え・切り花用と利用法が広い花の一つである。しかし、残念ながら標津のような気温の低い地方ではいい花は見込めないが、早めに苗づくりをして栽培すれば何とか花を咲かせることができる。
花の色も多く、いろいろな系統があるので利用法は広い。例えば、草丈の短いものは、花畑に、八重咲き、一代雑種は切り花用に向く。日当たりの良い場所で栽培することが大切。
育て方
暖かい本州などでは、秋に種をまいて霜よけをすれば春早くに花が咲くが、北海道では秋に種をまいて芽は出るが、冬の寒さで苗が枯れてしまうので、春早く3月下旬頃までに温室か部屋の中で種をまいて苗づくりをしなければ、花は望めない。
苗づくりは、発泡スチロールの箱か鉢などに種をまくが、種が小さいので覆土(種をまいた上に土をかけること)はほんの少し、種がようやくかくれるか、または種が所々見えるくらいでよい。
このような覆土をした場合、水かけのとき静かに少しずつかけないと種が流れて低いところに集まるので気を付ける。
できれば、種をまいた箱や鉢の下から水を吸わせるようにすればよい。方法としては、箱や鉢の下に水受けをおいて、水受けに水を入れるとよい。
図
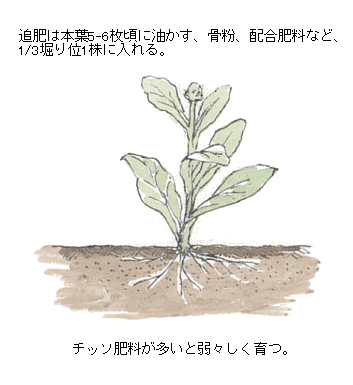 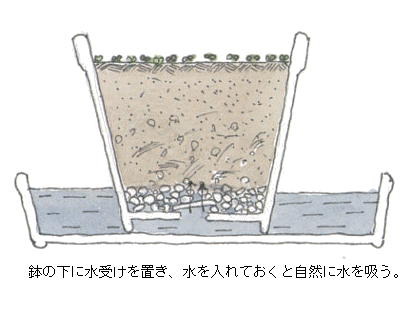 |
キンギョソウの発芽温度(芽が出やすい温度)は割合高く、25〜28度C位が理想的なので、温室か部屋の中でも温度の高いところに置くことが大切である。
本葉が2〜3枚でたら、1回目の移植を行う。2回目の移植は本葉5〜6枚のときに行う。ビニールポットにすると、本植のときに扱いやすい。
5月下旬〜6月上旬頃、気温が上がり、苗が蕾を持ったころ花畑やプランターなどに本植する。
この花はよく肥えた土でないといい花が咲かないので、花畑に堆肥をたっぷり入れて土を耕して植えるようにすることが大切である。
追肥も、植えた苗が根づき、育ち始めたら油粕・骨粉・配合肥料を1株に1/3握り、10〜15日に一度、2〜3回与えた方がよい。
春に花畑に直接種をまいても、ほとんど花はつかない。
図 苗づくり
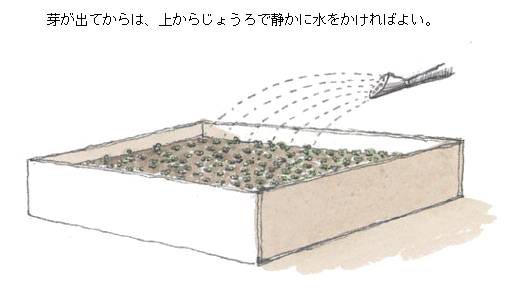 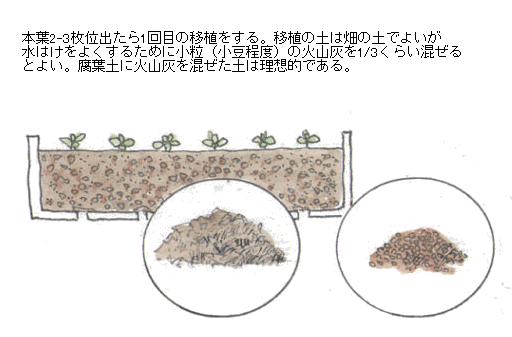 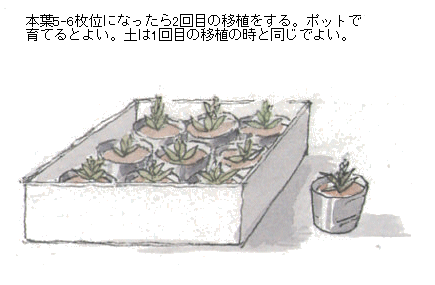 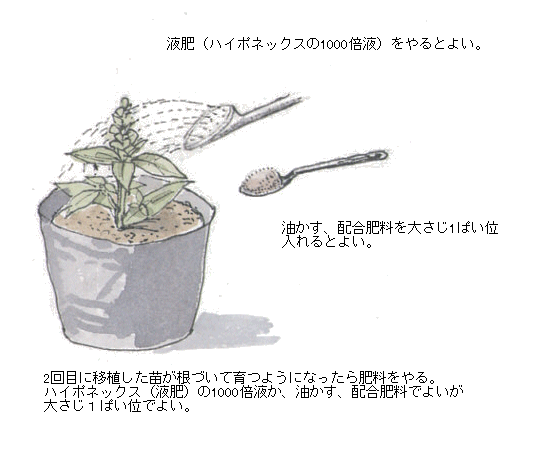 |
(12)ビジョナデシコ
原産地 アジア・南米
秋まきの2年草の花だが、標津のような寒い地方では、春の6月頃花畑に直接まくと次の年に花が咲く。この花は、花が付くまでに12か月以上かかるわけである。しかし、最近、種をまいた年に花が咲く1年草に改良された品種もできたようである。
花畑・鉢植え・切り花にも活用できる。寒さにも強い花で、花の色も多く、作りやすい花の一つで、ぜひ育てて欲しい花である。
育て方
6月上旬頃花畑に直接まくと、やがて芽がでる。本葉4〜5枚のときに間引きする。間引きした苗は移植して育てるとよい。
土は水はけのよい、よく肥えたものがよく、堆肥を入れて十分に栄養を与えて育てる必要がある。
追肥として、本葉6〜7枚になったら配合肥料・油粕・骨粉などの有機質肥料を苗1本に対して大さじ1杯程度与えるとよい。
この花は、低温(15度C)で花芽が出るので、寒い地方に向く花の一つである。
(13)パンジー
原産地 ヨーロッパ
寒さに強い花で、秋に種をまいて次の年の春に花を咲かせる。春の花壇にぜひ必要な花の一つであり、多くの家の庭やプランター、鉢などに植えられているのが見られる。
花の色も多く、花も大小いろいろある。パンジーの花は8月になると散ってしまうが、標津では、その年の気候条件にもよるが秋まで咲くこともある。標津のような寒い地方では花壇・プランター・鉢植えなどに活用したい花の一つである。
育て方
7月下旬〜8月上旬頃花畑に種をまくとやがて芽が出る。霜が降る10月下旬になると、本葉4〜5枚のものもあれば、蕾を持つものもある。時には花を付けるものもある。やがて土が凍るが、そのままにしておけばよい。春雪が解けると、雪の下で冬を越したパンジーが姿を見せ育ち始める。
土が解凍したら混んでいるところの移植をすればよい。6月中旬〜下旬になれば花が咲く。
しかし、5月上旬〜中旬に花畑やプランター・鉢などで花を咲かせようと思っても間に合わないので苗づくりをしなければならない。
苗づくりは、つくる場所によって種まきの時期が違う。
ビニールハウスの場合は9月上旬〜10月上旬頃に種をまき、11月下旬土が凍ったら苗の上に枯れ草で覆いをして冬を越せばよい。土が凍ったら水をかける必要はないが、凍らないうちは乾燥するので水をかけないと乾燥して枯れることがある。土が乾いたら水をかける必要がある。
4月上旬になると気温が上がってくるので、枯れ草を除いて育てると5月下旬〜6月上旬ころになると花が咲く。花が咲いたら花畑に植えるとよい。
早く花を咲かせようとするときは、トンネルにして温度を上げてやる。その年の春の気温にもよるが、4月上旬〜5月上旬には花が咲く。
温室の場合は、3月上旬頃種まきをして育てると、5月上旬には花が咲く。
いずれにしろ、苗の移植をしなければならない。花畑やビニールハウスにまいたときは移植をするときに土が凍っていることが多い。この場合は、春に土が解けてから移植した方がよい。秋遅くなってから移植すると、苗の根が十分でないうちに土が凍って盛り上がり、根を切断することも考えられる。春早いうちの方が安全である。
温室の場合は、いつでも温度が確保されているので、本葉3〜4枚のときに移植する。温室で苗づくりをする場合の注意としては、あまり温度を上げず、15度前後の方がしっかりした丈夫な苗ができる。太陽光線を十分に当てることも大切である。
肥料は、苗づくりの時は液肥プラントフットの1000倍程度を1週間に一度は与える必要がある。花畑やプランター・鉢などに植えたときは、植えてから1〜2週間で追肥として配合肥料・油粕・骨粉などの有機質肥料を1株に半握り見当でいれると、苗の生長もいいし、いい花が咲く。
大概の草花にいえることだが、花が咲いたあと雨が続くと花が腐ってくる。腐った花はていねいに取ってやるようにするとよい。しかし、たくさん栽培しているときは大変な仕事である。
(14)ケシ類
原産地 ヨーロッパ
秋まきの寒さに強い花畑用の越年草だが、標津のように寒い地方では春にまいた方がよい。花の色も多く、目だった花が咲く。花が長持ちしないのが欠点であるが、寒い標津には欲しい花の一つである。
気を付けなければならないことは、法律で栽培が禁止されているケシ類があるので注意が必要である。(厚生省より「ケシの見分け方」というパンフレットが発行されている。「植えて悪いケシ」「植えてよいケシ」の内容を記載します。
「植えて悪いケシ」
厚生大臣の許可を受けなければ栽培できないケシは、次の3種類です。このケシには麻薬の原料であるモルヒネ等が含有されており、特に「ソムニフェルム種」と「セティゲルム種」のさく果(けしぼうず)からは「あへん」が得られます。これらのケシは形態上の特徴を注意すれば、容易にほかのケシ属植物と区別することができます。
「植えてよいケシ」
ヒナゲシ・オニゲシ
育て方
ケシ類は移植を嫌うので必ず直接花畑にまくようにする。ケシ類は肥料分を欲しがるので種をまく前に堆肥をたくさん入れ、耕す必要がある。
種は小さいので、種をまいた上に土はかけなくて良いが、そのときは板などで表面をを堅く押さえるとよい。土をかけるときはほんの少しでよい。
種が小さいので、芽は早く出るが本葉が出たら間引きして3〜5㎝間隔にして育てるとよい。間引きした苗を移植してもよいが根付きは悪い。
肥料は、追肥として油粕・骨粉・配合肥料を1株に大さじ1杯ほど与えるとよく育ち、いい花を咲かせてくれる。
一度種をまくと、花から種が落ちて次の年に芽が出ることもあるが、あまり期待できない。
しかし、高山性のリンリヒナゲシのように一度種をまくと落ちた種でどんどん増える丈夫なケシもある。
草丈の高い品種もあって風で倒れることがあるので、支柱を立てる必要が出てくる。リンリヒナゲシの草丈は短く10㎝ほどである。
図
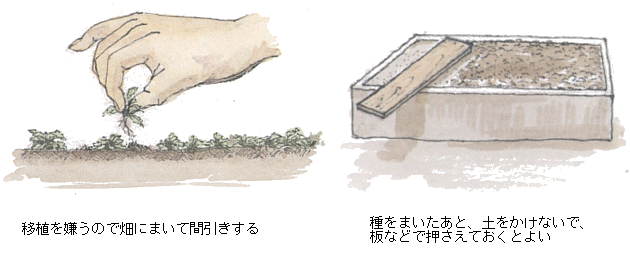 |