3. 1年草
(1)アサガオ
原産地 熱帯アジア
アサガオは奈良時代に薬用(下剤)として中国から入ってきた。江戸時代に花として栽培され広がっていった。
花の色・形・大きさはいろいろと多い。
一般に西洋アサガオといわれているものは大輪の花が咲き、つるはあまり伸びないので鉢植えに利用されることが多い。
日本アサガオといわれているものは、ツルアサガオともいわれ花は小さいが数が多い。ツルアサガオといわれるように、ツルがかなり伸びるので花畑に植え、棚を作ったり、棒を立てたりしてツルを誘導してつくると良い。
育て方
アサガオは元々は熱帯性の植物なので、気温は高い方がよく育ち、特に大輪の花が咲く西洋アサガオは、標津では気温が低いため花畑で栽培しても咲かないことが多い。鉢植えをして気温の高いところ、例えば家の中、ビニールカウス・温室などでないと花を咲かせてくれない。
日本アサガオ(ツルアサガオ)は西洋アサガオよりも低温に強いので、標津の花畑でも十分に花を咲かせてくれる。
種は、花畑に直接まいてもよいが、できれば家の中・ビニールハウスで苗づくりをし、本葉2~3枚のときに花畑に移植して育てた方がよい。移植は10~20㎝程度の間隔に植え、棒を立てるか棚を作って誘導するとよい。ツルは4~5m程伸びる。
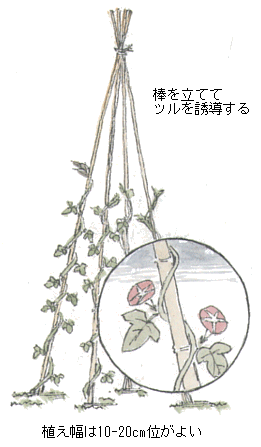 |
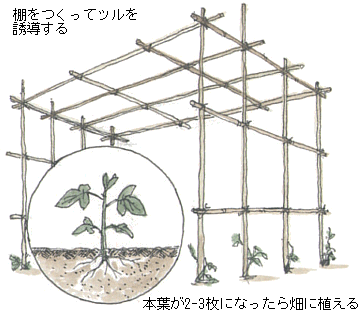 |
土
西洋アサガオを鉢植えする土は、畑の土5・川砂(火山灰・鹿沼土でもよい)5・腐葉土5の割合に混ぜたものがよいが、水はけがよく、肥料分の多い、肥えた土であればよい。
腐葉土というのは、広葉樹(葉の大きな木のことで、松類は針葉樹という)の葉が腐って土になったものであるが、土にならなくても腐ったような葉であれば使ってよい。
花畑で栽培する日本アサガオの場合は、特別に土を選ばなくてもよいが、堆肥の入った、水はけのよい、よく肥えた土が望ましい。
図 鉢植えの土
 |
鉢植えの場合の土の入れ方
 |
肥料
鉢植えの場合、鉢に入れる土に油粕5・骨粉5の割合で混ぜた肥料を一鉢に一握り入れ、土とよく混ぜて使うとよい。
花畑の場合は、種をまくときに油粕・骨粉を種をまく場所に軽く入れ、土とよく混ぜ、少し土をかけてまくとよい。
図 鉢植えの場合
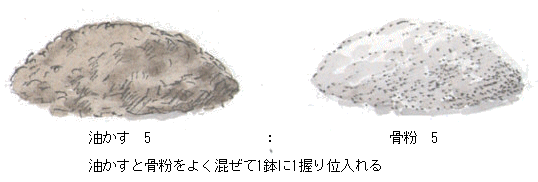 |
(2)コスモス
原産地 メキシコ
花畑にも街道にも山の斜面にも平らなところにも、たくさんでも少しでも、なんとなく似合うの花の一つである。
春まきの1年草で、代表的な短日性植物なので、日が短くなった秋に花が咲く。春早くまいても、花が咲くのは9月頃、日が短くならないと花は咲かないので、急いで種まきをしなくてもよいといわれる。しかし、これは暖かい地方のことで、標津のような寒い地方では少し早くまかないと、花の咲く時期までに草丈が伸びないので、6月上旬頃までには種まきをする必要がある。
日の長さに関係なく花が咲くセンセーション系という早咲きのコスモスもある。このコスモスは、種をまいてから70日程度で花が咲くので、標津のような寒い地方に向く花といえる。
図
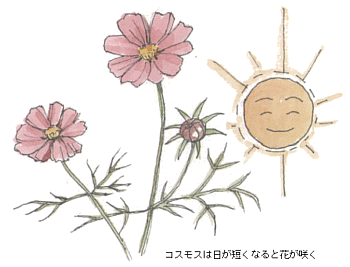 |
育て方
苗づくりをして花畑に植えてもよいが、直接畑にまいても立派な花が咲くので、苗づくりをする必要はない。
コスモスは、茎が伸びやすく、枝が出やすいので、風によって倒れやすい。特に密生させると枝はあまりでないが、茎が細く、丈が長くなって弱々しい茎に育ちやすいので、少し離して植える(10~20㎝)と茎は丈夫になり、枝もよく出て倒れることが少ない。
種をまきすぎて、密生してしまった場合は移植するとよい。移植に強い花の一つである。
日当たりの悪い場所に植えると、茎も細く、枝も花も少なくなるので、日当たりの良いところに植えることが大切である。
図
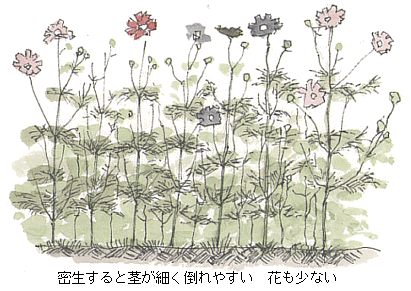 |
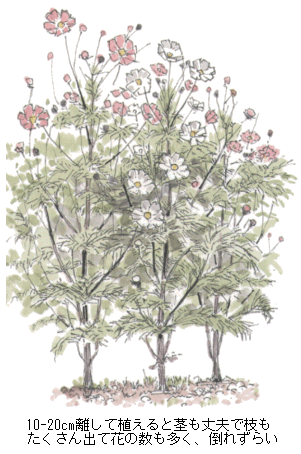 |
肥料
コスモスは、土の中の養分をたくさん吸収するので、あまり肥料を与えなくてもよいが、やせた、肥料分の少ない土では育ちも悪いし、花も少なく、小さく数も少ないので、やせた土の場合は、種をまく前に堆肥を入れてたがやしてから種をまくようにする。追肥の必要はない。
(3)サルビア
原産地 南米ブラジル
原産地が暖かい地方なので、温度がある程度高くないと花が咲かない。標津のような寒い地方では、いい花を咲かせることは難しい。どうしても苗づくりをして花畑に植えなければ、いい花どころか花が咲かない。したがって、苗を作る場所、温室が必要となってくる。ビニールハウスでは苗づくりが遅れてしまい、いい花は望めない。少しなら家の中でも苗づくりができる。
育て方
日当たりが良く、風当たりの少ない場所が良く、土はよく肥え、酸性が弱く、水はけも良くないとよく育たない。日照時間の少ない低温の年には、いい花を期待できないと考えてよい。しかし、花畑にほしい花の一つである。
サルビアの発芽温度(芽の出やすい温度)は高いので、直接畑に種をまいても標津での発芽は望めないので、苗づくりをし、花畑に移植して育てなければならない。
苗づくりは、3月下旬~4月上旬頃、家の中か温室に種をまいて苗づくりをし、蕾を持ってから花畑に植えるようにする。花畑に植えるのは、気温が高くなってからなので、6月中旬頃である。
苗づくりで大切なことは、発芽温度が30度C程度必要なので、温度を高くすることである。移植は本葉2~3枚のときに1回目、2回目は本葉5~6枚になってからビニールポットに移植するとよい。そうすると、花畑に植え替えるときに楽である。1回目の移植は発泡スチロールでよい。
花畑に堆肥をたくさん入れ、酸性を和らげるために石灰(炭カル)も入れて耕て植えるとよい。
とにかく低温の場合は育ちも良くないし、花つきも悪いので、サルビアを花畑に植える場合は、風の当たらない、日当たりの良い場所を選ぶことである。
図
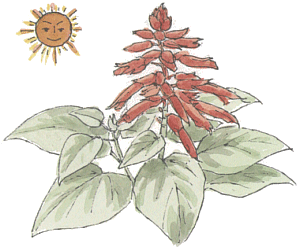 |
風が当たらず、太陽光線がよくあたる日溜まりに植える。このような条件がないときはプランターを使う。
(4)ハボタン
秋も深まって、日中の気温が上がっても夕方から肌寒い頃になると、ハボタンはますますいい色を出す。
寒さに強く、少々の霜には全く関係なく、1・2回の雪なら元気でいる。標津のように気温に落差のある地方には、多少の手間がかかるが最適な花である。しかし、あまり見かけない。ハボタンは花が咲くのではなく、葉にいろいろな色を付ける植物である。
種
優良品種といわれるハボタンの種はたくさん取れないので、粗悪な種を販売していることがある。いい種を手に入れるのは難しい。悪い種では、葉にいい色が付かないといわれています。
苗づくり
あまり早くまくと大株になり、本植えのときの取り扱いが面倒なので、6月中旬~下旬に発泡スチロールの箱にまく。発芽温度は高くないので屋外に置いてもよい。
本葉3~4枚で1回目の移植をするが、苗が小さいので発泡スチロールの箱がよい。本葉7~8枚になったら2回目の移植をする。このときは畑でよい。本植は苗の生長にもよるが、8月中旬~下旬になる。苗づくりでは、移植の回数を多くしないと弱々しい苗になり、根の出も悪いので、最低2回移植の必要がある。また、移植を行わないと根元の葉がとれやすく、茎が長くなり醜くなる。もし、根元の葉がとれて茎が長くなったら、深植をして、地上すれすれに葉があるようにするとよい。切り花にするときは茎が長くてもよい。 花畑に利用するときは、同色のものを一カ所に20~30株植えると見栄えがする。
植えるときは、葉と葉が付くように植え、畑の土が上から見えないようにするとよい。
図
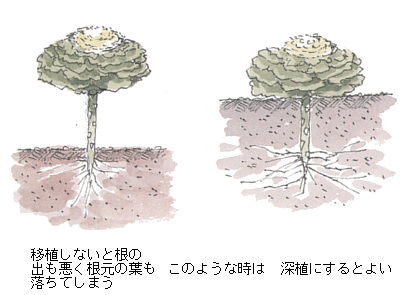 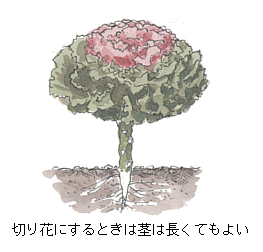 |
肥料
窒素肥料が多いと葉が大きくなりすぎ、色付きも悪いので、植えるときの肥料は入れないで、追肥として1株に一握りの骨粉を与えるとよい。
青虫が付いて葉に穴をあけるので、ていねいによく見て取ってやる。
(5)ヒマワリ
原産地 メキシコ
性質は強く、肥えた土でもやせた土でもよく育つ。本来なら炎天下、太陽を仰いで咲くが、標津のような寒い地方では夏になっても咲かない年もあるが、8月上旬には咲く。ヒマワリといえば、茎の頂上に一つだけ花が咲くと考えるが、品種改良によって、枝が出て咲くものや、草丈が伸びずに低く咲くものもある。花の色も黄色だけではなく、樺色や赤みを帯びた花もある。また、八重咲き、菊咲きなどの形もある。
育て方
なるべく早くまいた方が草丈も高く、花も大きくなるので、5月中旬~下旬頃までに種まきをした方がよい。
まき方は、畑に直接まいた方がよく育つ。苗づくりをして移植してもよいが、畑に直接まいてもよく育ち、いい花が咲くので苗づくりはしなくてもよい。ヒマワリの種は小鳥の好物なので、スズメなどに見つからないように種は必ず土の中に埋める。一粒でも見つかると、全滅することがある。
肥料分が多いよく肥えた土につくると、大きく育ち、大きな花も付けるが、風で倒されることもある。この場合、支柱が必要になるので、風当たりの少ない場所が理想的である。
ヒマワリは太陽の光を欲しがるので、日当たりと水はけが大切である。できれば少しつくるのではなく、たくさん作った方が見栄えする。
図
 |
(6)マリーゴールド
原産地 メキシコ・アルゼンチン
花を付けている期間が長く、肥料さえ与えておけば夏から秋まで咲いてくれる。強い草花の一種であるが、標津では少々温度が不足で、気温が低い年はよい花が咲かないこともある。特に、霧による日照不足、温度不足の影響が大きい。
切り花、花畑、鉢物として利用されるが、室内に置くと特有の匂いがあるので進められない。最近は、品種改良によって匂いの少ないものもある。
マリーゴールドは、短日性(日が短くなると花が咲く)と、長日性(日が長くなると花が咲く)の品種があるので、長日性は夏の花畑、短日性は秋の花畑と上手に組み合わせて利用することができる。
アフリカン系は長日性、フレンチ系は短日性だが、種が入っている袋に書いてあるのでよく読んで購入するとよい。
育て方
標津では、花畑に直接種をまいても花は望めない。苗を作って花畑に植えなければならない。苗づくりは4月上旬頃、温室かビニールハウス、室内に種をまいて2回位移植して苗を作るとよい。
発泡スチロールや鉢などに種をまくと、一週間程度で芽が出る。芽が出て10~15日で本葉が2~3枚出るので1回移植し、その後苗の伸び具合を見て、本葉5~6枚になったら2回目の移植をする。
図
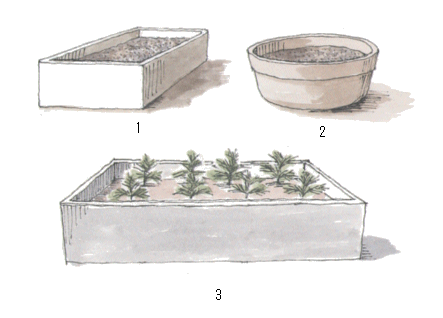 |
一回目の移植は、発泡スチロールの箱がよく、土は種をまくときと同じでよい。2回目の移植は、ビニールポットにした方が花畑に植えるときの取り扱いが楽である。
4月上旬に種をまくので、土は前の年に確保しなければならない。
図
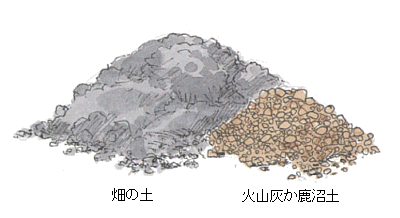  |
畑に植えるときの苗は、花がつき始めたものがよい。しかし、種まきが早かったり、温室やビニールハウスや室内で苗を育てるとき、温度が高く成長の条件がよいと苗の花つきが早すぎて畑に植えてもよい程度の苗になっても、外気温が低く植えられない場合もある。こんなときは、花を取ってやるとよい。花を取ると枝がたくさん出るからである。6月中旬頃になると気温も上がるので、畑に植えるとよい。気温が低いと苗が茶色になり成長が止まることがあるが、気温が上がると新しい芽が伸びて立派な花を咲かせてくれる。
肥料は、堆肥を入れて耕してから植えれば追肥の必要はないが、肥料分が不足すると花付きが悪く、草丈も低いので、このようなときは追肥として市販の配合飼料を一株に半握り程度入れてやる。
植える場所は日当たりの良い所を選ぶことが大切である。