3)草花の増やし方
①増やし方のいろいろ
草花を増やす方法にはいろいろある。種をまいて増やす方法、株分けして増やす方法、さし木して増やす方法、取り木をして増やす方法、このほかユリをりん片で増やす方法などいろいろである。
②草花の種とり
草花には、花が咲いたあと実がなる。この実が種になるのがほとんどである。
草花によって花の咲く時期、期間が違うのと、花が咲き終わってから種が完熟するまでの期間が違うので、何月頃取るということを一概には決められないが、種が完熟すると種を包んでいる「かく」の色が変わるので「かく」をよく観察すれば大体のことはわかる。
種類によっては、とり方が遅くなると実がはじけて種が飛び散ってしまうものもある。また、とり方が早いと、熟していないので芽が出ない。熟していない種の大部分は種の色が白っぽく柔らかい。だから、とる時期が大切になる。もちろん、霜が降る前に取ることが大切である。ツツジ・シャクナゲなどは霜が降ってからでもよい。
長い期間花が咲く草花は、種を付けないように花が傷んだら摘み取るようにし、肥料を十分に与える。そうすると、株が老化せず長い期間花を付ける。
家庭では種をたくさん必要としないので、種とりように何株か育てておけばよい。
園芸改良種の場合は、毎年新しい種を買って育てた方がよい花が望める。特に一代雑種(F1)と種の袋に書かれているものは、種を取って育ててもいい花を望めないし、花が咲かないこともある。一代雑種以外のものは、種を取って育ててほしいものである。自分で取った種をまいても十分な手入れをすれば、いい花を咲かせてくれるし種も取れる。
サルビア・コスモス・ヒマワリ・アサガオ・カスミソウ・ワスレナグサ・キンセンカ・キンレンカなどは、ぜひ種を取ってほしいものである。
山草類や高山植物も種を取って育てるとよい。山野草、高山植物、多年草類は「とりまき」といって、種を取ったらすぐにまく方法がよいので保管の必要はない。
一年草の場合は、次の年の春に種をまくので保管しておかなければならない。
図 種の保管
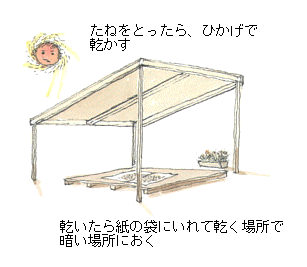 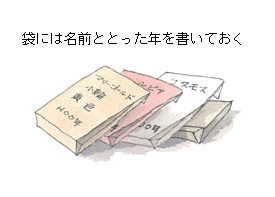 |
花畑でたくさん育てたいときは、種をまくが、100粒まいても100の芽は出ない。概ね60%位。場合によっては20%位しか発芽しないこともあるので、そのつもりで種まきをした方がよい。
とにかく、自分で種を取ってまくと一度にたくさんの苗もできるし、時には親と違うものも出ることがあるので楽しみもある。なんといってもお金がかからないことが魅力である。
③株分けをして増やす方法
秋に茎が枯れても根が残って冬を越し、春に新しい芽を出して花を咲かせてくれる草花を「宿根草」といっている。
宿根草は花が咲いても種を付けないものが多いので種で増やすことは難しいが、幸いなことに地下茎が株になるので株分けをして増やすことができる。
株分けの時期や方法は草花によって違うが、概して春か秋である。
a春に株分けをする宿根草
ジャスターデージー・ギボウシ・キク・アスチルベ・エビネ・オダマキ・ゼラニウム・ベゴニア・クリンソウ・サクラソウ・ホタルブクロなどである。
図 キクの株分け
 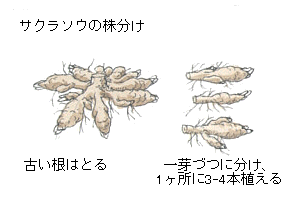 |
b花が終わったあとすぐに株分けする宿根草
ハナショウブ・アヤメ・アイリス・アルメリア・イカリソウ・ケマンソウ・ジャガなどである。
図 ハナショウブの株分け
  |
アヤメの仲間は一度咲いた株は二度と咲かないので植えない。まだ花を付けたことのない若い株を2〜3株以上付けて植えないと次の年花が咲かない。
c秋に株分けする宿根草
シャクヤク・スズラン・フクジュソウ・プリムラ・キキョウなどである。
図 シャクヤクの株分け
  |
④挿し木をして増やす方法
挿し木とは、植物の体の一部を切って土(火山灰・ピートモス・バームキュライト・水ごけなど)にさして根を出させて増やす方法である。
挿し木の良い点は、親と全く同じものができること。元気のなくなった木や草花の枝などを挿し木により全滅しないようにできること。突然変異で変わった花が咲いたとき、挿し木により同じ花を増やすことができること。短い期間で花を咲かせることができる。などである。
欠点としては、一度に大量に増やすことができないこと。挿し木したものすべてが完全に根を出して育つわけではなく、枯れてしまうものも多い。などである。
しかし、一度は挿し木の方法で増やしてみたいものである。
a挿し木の手順
親株を選ぶ
さし穂をとる よく伸びた元気のよい枝先をとる。
2〜3節15㎝位の長さ
さし穂の調整 下葉の整理をする
節のすぐ下を切れる刃物で切る
さし穂の処理 水に10分〜20分位つけておく
さし床づくり 土は火山灰(粉を除く)
バーミユキライト・ピートモスなどでもよい
挿し木 さし床に穴をあけてさし穂をさす。
根元を軽く押さえる
管理(手入れ) 乾かないようにする
適温で管理する(25度C位)
b挿し木の方法
 |
挿し木をする土は、水はけのよい清潔な土でなければならない。例えば鹿沼土、火山灰、バーミュキライト、ピートモス、水ごけ、川砂などである。火山灰、鹿沼土は、目の細かいふるいで粉を取り除いた小豆粒か花豆位の大きさの粒がよい。水ごけはよく乾燥して細かく砕き粉状にして使うとよい。水ごけは完全に乾燥すると水を吸収しないので、使う前日にバケツに水を入れ、その中に粉状水ごけを入れて上から軽く重石をして置く必要がある。
鉢や発泡スチロールの箱などで挿し木をするが、容器の下の方には粒の大きな火山灰、鹿沼土、赤玉土を入れて水はけをよくする。その上にふるいで粉を取った火山灰、鹿沼土、バーミュキライト、ピートモス、川砂などを入れて挿し木すればよい。
図 挿し木用の土の配分
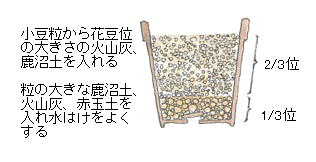 |
箱を利用する場合も大体同じ割合で土を入れるとよい。容器の上の方に入れる土は川砂、バーミュキライト、ピートモス、水ごけでよい。
挿し木をしたら直射日光の当たらない半日陰の所に置き、水を切らさないように土が乾燥したら水をかける。水が切れると枯れると考えてよい。
根の出やすい温度は割合高く25度C位は必要なので、温度が低い場合は上げる工夫をしなければならない。例えばビニールで囲う、ビニールハウス・温室・室内などに置くようにするなどである。
肥料は、根が出て伸び始めるまではやらないようにする。根の出る前や根の出始めに肥料をやると枯れることが多い。
根が出たかどうか挿し木を引っ張って見ることはやめた方がよい。せっかく出始めた根が切れるからである(気持ちはわかるが)。
植物の種類、温度管理などによって根が出る日数は変わるが、根が出ると植物は育ち始める。
移植は、完全に根が出てからの方が安全である。
この他に芽さし、茎伏せ、根伏せ、りん片さしなどの方法もあるが手数がかかるので省略する。
4)肥料は上手に使いたい
①草花と肥料
植物は、元気よく育てなければ長い期間花も咲いてくれないし、いい花も咲いてくれない。元気に育てるためには、気温、日照、水分、土、日常の管理も大切であるが肥料も大切な条件の一つである。
肥料を植物が必要とするだけ与えておかないと肥料切れになり、株も早く枯れるし、花も咲いてくれない。一般的に1・2年草はたくさんの肥料を欲しがり、宿根草は1・2年草より少なくても立派に育ち花も咲く。しかし、植物に体力がないと花も少なく、小さくなりいい花が咲かないので、宿根草にも春先には十分な肥料を与えた方がよい結果が出る。
山草類は、あまり肥料を与えなくてもよいが、生育期間の短いフクジュソウ・カタクリ・マイヅルソウ・ゴゼンタチバナなどには肥料を多く与えた方がよい。
②有機質肥料と化学肥料
a有機質肥料
(ア)有機質肥料とは
一つは有機質肥料で、植物を栽培する前に土の中に入れておく肥料のことで、堆肥や緑肥がその代表であり、鶏糞、油粕、魚かす、米糠、骨粉、草木灰、腐葉、野菜くずなどである。
有機質肥料は、与えたらすぐ効果が出るものではなく、少しずつ長期に渡って効果がある肥料である。特に、堆肥や緑肥は肥料としての効果だけでなく、植物を育てる大切な土の条件をよくするので、できるだけ多く入れることが望ましい。多く与えても肥料やけしない。
しかし、有機質肥料も含まれている成分がそれぞれ違うので、使い方に注意が必要である。
有機質の肥料成分(別表)
堆肥、緑肥は茎肥として使う。他の有機質肥料は基肥として使ってもよいが、追肥といって植物の成長中に使ってもよい。しかし、効果が出るまで多少時間が必要なので、早め早めに与えるようにしたい。
図 肥料分の吸収のし方
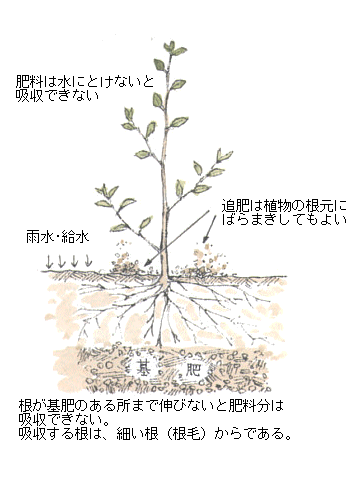 |
(イ)草花の肥料の与え方は、元肥と追肥の二本立てである。
元肥は、定植の時、堆肥に油粕、骨粉、魚かす、鶏糞などを混ぜて穴の底に入れる。混ぜるのが面倒なときは、穴の一番下に堆肥、その上に油粕、骨粉、魚かす、鶏糞を入れるとよい。
球根のダリア・グラジオラスなど毎年植え替える草花は、多くの元肥を必要としないが、シャクヤク・アイリス・スイセンなどは毎年植え替える必要がないので、植え替えの時基肥を十分に与えておく必要がある。
図 ダリアの植え方 スイセンの植え方
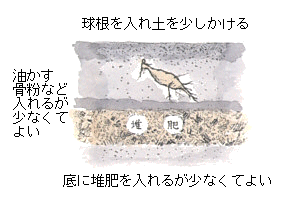 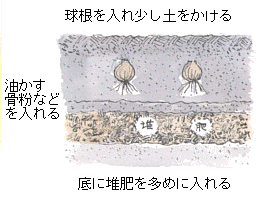 |
(ウ)肥料は、土の性質によっても効果が違う。
標津の土である火山灰や泥炭土では、りん酸肥料を多く与える必要がある。理由は、火山灰や泥炭地はりん酸分が水に溶けにくいからである。
肥料は与えたら与えただけ効果があるのではなく、実際に植物が肥料分として吸収できるのは20〜30%程度で、残りは流されてしまう。たくさん与えたと感じても実際には多いわけではない
普通の草花は、肥料成分で窒素(N)1・リン酸(P)1・カリ(K)1.2の割合でよいが、標津の土は火山灰か泥炭土なので、リン酸を2以上与えた方が良い結果が出る。
火山灰・泥炭土の肥料の与え方
窒素(N)1:リン酸(P)1:カリ(K)1.2
の割合だがリン酸は「2」以上与えてよい。
(エ)多年草の場合は、追肥として与えることになる。
春、暖かくなると植物の芽が動き出す。この頃に油粕と骨粉を同じ割合で混ぜて、株の根元に一握りか二握り程度ばらまきしておけばよい。木灰を一握り与えると理想的である。
市販されている配合肥料でもよいが、配合肥料はそれぞれの肥料成分を混ぜている。その割合は袋に書かれているので、よく読んで使うことが大切である。
(オ)市販の配合肥料
配合肥料
肥料成分が書かれている
| 窒素(N) | リン酸(P) | カリ(K) |
| 1 | 1 | 1 |
| 窒素(N) | リン酸(P) | カリ(K) |
| 2 | 3 | 3 |
標津の土に合う肥料
| 窒素(N) | リン酸(P) | カリ(K) |
| 少ない | 多い | 多い |
b化学肥料
化学肥料は、科学的に作られた肥料で、主に窒素、リン酸、カリの3成分である。
窒素肥料には、尿素、硫酸アンモニア、石灰窒素。リン酸には過リン酸石灰、溶性リン肥。カリ肥料には石酸カリ、塩化カリなどがある。
化学肥料は、早く効果が出る肥料であるが、多く与えると肥料やけを起こし、時には植物が枯れることもある。また、窒素肥料を多く与えると、茎や葉ばかりが繁って花付きが悪く、病気にもかかりやすくなる。リン酸、カリ肥料は少々多く与えても害にはならない。
市販されている肥料に野菜用の肥料があるが、この肥料をそのまま与えるのは窒素分が多いので草花向きではない。草花用の肥料を使うようにした方がよい。
化学肥料を水に溶かして使ってもよいが、なるべく薄くして使うようにする。100倍の液を1回与えるより200倍にして2回与える方が効果があり、安全である。