(8)増やし方、育て方
1)種のまき方
1~2年草は、種から育てるのが普通である。種は鉢や箱のような容器にまくものと花畑に直接まくものとがある。早く花を咲かせたいときは、温室・室内・ビニールハウスなどで鉢や箱にまいて苗づくりをしてから花畑に移植すればよい。
①種をまく土は清潔な土がよい
種をまく土は清潔で肥料分のない土の方がよいが、花畑に直接まく場合は清潔な土といっても、土の入れ替えもできないのでよく耕し、土の表面をよく砕いて種をまくようにする。
鉢や箱にまくときの土は清潔で肥料分のない土を使うようにする。
具体的にはバーミキュライト、ピートモス、火山灰の小さな粒、水苔の粉末などである。このような土は、病原菌・肥料分がない清潔な土である。
このような土がなく、どうしても畑の土を使わなければならないときは、熱湯消毒をして完全に冷ましてから使うとよい。
しかし、一般の草花などの種まきは畑の土でも芽が出るので、水はけを良くして使うとよい。水はけを良くするためには、火山灰の小さな粒を入れるとよい。
土の用意ができたら種をまくが、種をまけばその上に土をかけるのが普通であるが植物によっては土をかけない方がよいものもある。微粒種といって粒の小さな種はあまり土をかけない方がよい。
例えばロベリア・ペチュニア・キンギョソウ・コリウス・ベコニア・カランコエ・ワスレナグサ・ジギタリス・パセリ・チシヤ・ミツバ・シクラメン・プリムラなどがある。
| 図 粒の小さな種のまき方 |
 |
種をまいたあと土をかけない理由は、粒が小さいと種に光が当たっても十分芽が出るからである。また、水も上からかけない方がよい。その理由は上から水をかけると種が流れて低いところに集まってしまうからである。水は、鉢や箱の下から吸わせるようにするとよい。発泡スチロールの箱に種をまくときは、箱の底に必ず穴をあけることを忘れないようにする。
②大粒の種のまき方
大粒の種、例えばケイトウ・アスター・マリーゴールド・アサガオ・ルピナス・オジギソウ・ナス・カボチャ・ダイコンなどがある。
種をまく土や鉢、箱に土を入れる割合などは粒の小さな種と同じでよいが、種をまいたあと、種の上に細かい土をかける。かける土の厚さは、種の大きさの約3倍位である。水も上からかけてよい。種が土の中にあるので流れることがないためである。粒が小さい種は光が当たっても芽を出すが、大粒の種は光りを嫌う傾向があるので種の上に土をかけた方がよいのである。
| 図 大粒の種のまき方 |
 |
水は上からかけて良い。大粒の種は芽を出すために光りを嫌うので、種をまいた上に種の大きさの3倍位の厚さに土をかける。
種をまいたら、乾燥させないように管理すると芽が出る。芽が出るまでの日数は草花によって異なる。
③発芽までの日数
適温・適湿で管理した場合芽を出すまでの日数は
4~5日位 コスモス
7~8日位 ヒャクニチソウ・マリーゴールド・アゲラタムなど
10日~12日位 キンレンカ・ペチュニア・パンジー・カスミソウ・ケイトウ・マツバボタン・アスター・キンギョソウ・ダリアなど
14日~16日位 オシロイバナ・アフリカホウセンカ・サルビア・スイートピー・センニチソウ・ニチニチソウなど
20日前後位 ロベリア・バーベナなど
④発芽温度
昼と夜との温度に差がありすぎたり、水分が足りなくて乾燥したりすると芽を出さないことがあるので注意が必要である。
花畑に直接種をまく場合は、気温が上がってからの方がよく芽を出す。気温が低いと、芽を出すまでの日数がかかるが芽は出る。
芽を出すためによい温度(発芽適温)は植物によって違う。
主な草花の発芽適温は
20度~25度C位
アフリカホウセンカ(インパチェス)・オジギソウ・オシロイバナ・キンセンカ・ケイトウ・コリウス・セイヨウアサガオ・ゼラニウム・ニチニチソウ・ニホンアサガオ・ペチュニア・マツバボタン・アスパラガスなど
20度C位
アリッサム・ガーベラ・サルビア・スターチェス・センニチソウ・ハボタン・パンジー・ビジョナデシコなど
15度~20度C位
アゲラタム・アネモネ・アイスランドポピー・オニゲシ・カスミソウ・カーネーション・キキョウ・キキョウナデシコ・キンギョソウ・サクラソウ・スイートピー・ホーセンカ・マーガレット・ヤグルマソウ・ユリなど
15度C位
マリーゴールド・クレオメ・デージー・タチアオイ・ダリア・ヒマワリ・アザミ・ワスレナグサなど
10度~15度C
セイヨウオダマキ・アスター・キンセンカ・アルメリア・キンレンカ・コスモス・カイザイク・ナデシコ・ルピナスなど
10度C位
ヒナゲシなど
このように、植物によって芽の出やすい温度が違うので、花畑に直接種をまくときは気温に気をつけて、いつ頃種をまくかを判断しなければならない。特に、標津のように春の気温が低い地方では、気温が上がるのを待っていると種まきが遅れてしまうので、秋まで花が咲かないでガッカリすることがある。
このようなことのないように発芽適温の高い草花は温室、室内で発芽させ、苗づくりをしてから育てた方がよい。ビニールハウスの効果も大きい。
2)苗の移植
①苗の移植方法
種をまいて芽が出たら肥料を与えた方がよい。種をまく土は肥料分のない清潔な土なので、芽が出て植物が生長しようとしても肥料分がないと成長が悪くなってあたりまえである。球根の場合は球根に養分があるのである程度の期間肥料を与えなくてもよいが、粒の小さな種は養分が全くないと同じであるので肥料を与えないと成長が悪くなる。
与える肥料は液体の肥料が最もよく、1500倍~2000倍に薄めたハイポネックスを給水を兼ねて与えるとよい。
芽が育ち、本葉2~3枚になった頃1回目の移植を行い、本葉5~6枚になった頃2回目の移植をして苗が伸び始めたら少し濃い1000倍~1500倍位の液肥を与えるとよく育つ。
ビニールハウスで苗を育てるとき、寒い夜は新聞紙、ビニールなどをかけて保温し苗を凍らせないように注意する。反面、日中温度が高くなっているのに保温のためのビニールをそのままにしておくと温度が上がりすぎて苗を枯らすことがある。
苗が順調に育っているときに少しの不注意で苗を全部枯らしてしまったなどは、よく聞く話である。
| 図 移植の仕方 鉢にまいた種は、芽が出て本葉が2~3枚出たら1回目の移植を鉢や箱にする。 |
|
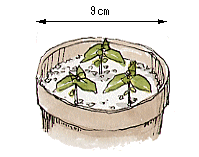 |
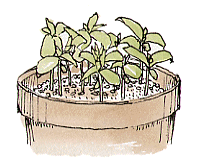 |
| 9cmでは3本植える | 鉢に種をまいて本葉が2~3枚出たら |
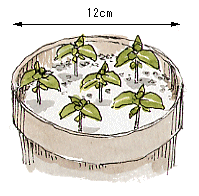 |
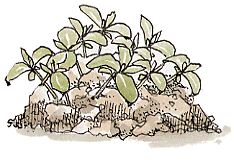 |
| 12cmでは6本植える | 鉢から抜いて根の土を崩して1本づつ移植する |
箱やプランターに移植する場合 |
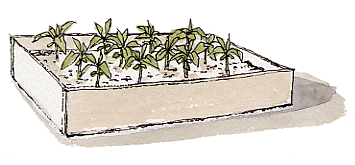 |
| 苗と苗の間を3~4㎝位離して植える 移植が終わったら水を十分かけて土を落ち着かせる。 |
苗は何のために移植するのだろうか。根をたくさん出させてよく育つようにするためです。移植しないと根の出が少ない。移植をするとどうしても根を切ってしまう。植物は、根を切られると根をたくさん出す性質があり、根をたくさん出すとよく育つようになる。
| 図 移植と根 | |
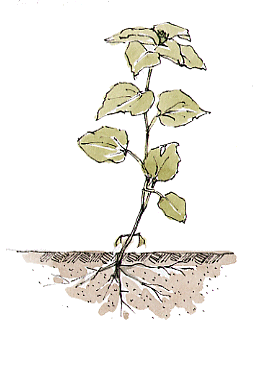 |
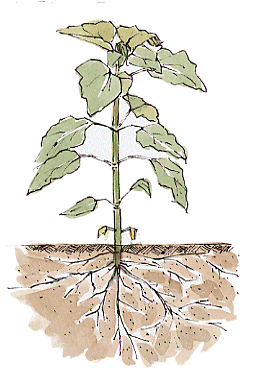 |
| 移植をしないと苗の根の数が少ない | 移植すると苗の根がたくさん出てよく育つ |
移植は1回より2回の方がよいようだが、1回でもいい。標津のような寒い地方では,
2回移植すると花畑に植える時期が遅くなるので、1回の移植で花畑に植えた方が結果が良い。
プランターや鉢、箱などで育てるときは、1回目の移植時に直接プランターや鉢、箱に移植して育てた方がよい。花畑で育てるときは、ビニールポットに移植しておくと便利である。
| 図 | |
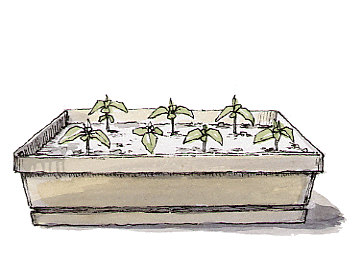 |
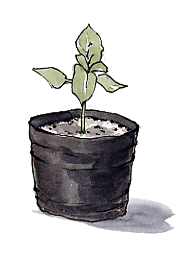 |
| プランターや鉢・箱で育てる時は、 1回目の移植の時に植える |
畑に植える時はビニールポットに 植えると移植すると畑に植えやすい。 |
②草花には移植を嫌うものもある。
マメ科、ケシ科植物は、直根性といって太くて長い根が深く土の中に入っており、一般に移植を嫌う。
例えば、スイートピー・ヒナゲシ・ポピー・ケシ類・アサガオ・ヤグルマソウ・ユウガオ・フウセンカズラ・ケイトウ類などは移植を嫌う草花である。
このような草花は、できるだけ小さな苗の時に移植しなければ根付きが悪く、枯れることがある。できれば移植しない方がよい。
③苗の植え方
植えたらその場所で最後まで育てることを定植という。花畑に植える場合はほとんど定植である。定植のときの植え方は、植える花畑をよく耕して、土の中によく空気を入れ、土を柔らかくし、水はけを良くして植える。植える4~5日前によく耕して準備しておいた方がよい。また、土の条件、例えば有機物が少なくやせている土とか酸性の強い土、水はけの悪い土は、できるだけ改良しておいた方がよい。
苗に付いている土と、花畑の土が違う場合には苗の根を傷めないように苗の土をとって植えた方がよいが、どうしても苗の根を傷めるので、ビニールポットで育てた苗は花畑にビニールポットよりやや大きめの穴を掘り、ビニールポットを逆さまにして静かに苗を抜き取って植え、その根元を軽く押さえておくとよい。ビニールハウスの床で苗づくりをした場合には、苗の根を傷めないように根を大きく掘り起こし、土を根にたくさん付けて植えるようにする。
植え終わったら十分水をかけておくが、土が十分湿っている場合は多少茎や葉がしおれていても水をやらなくてもよい。
気温の低いときに水をやりすぎると、植えた苗の根が冷えて傷むことがある。また、水分が多すぎると、根ぐされになるからである。
| 図 定植の仕方 | |
 |
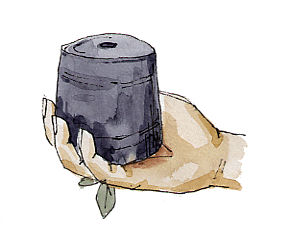 |
| 苗の根本に指を入れて苗をおさえ、 ビニールポットを逆にする |
ビニールポットを逆にしたら、ビニールポットを抜くと、 苗の根が傷まず、土もたくさん付く |
花畑にビニールポットより大きめの穴を掘って、 その中に苗を植え、根本を軽く押さえる。 終わったら水をかける。 |
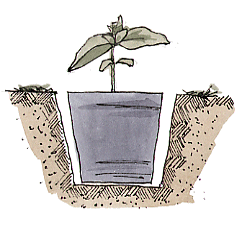 |
| 深く植えないように注意する。 |
このようにして植えると、苗の土が落ちにくい。
植えた苗に元気がなく、毎日水をやることがあると思うが、苗が元気でない原因には水や肥料のやりすぎもあるので注意が必要である。
肥料は苗が伸び始めてから与えた方がよい。苗を植えてからすぐに肥料をやったり、苗を植える穴に化学肥料をたくさん与えると、肥料やけをおこして枯れることがある。