「標津の花づくり」の索引を表示
総論
1.はじめに
美しく咲いた花を見て、腹を立てる人はいないが、花を見て心を和らげる人は多い。
自分で花を育ててみようかな! と思う人も多いが育て方がわからないし、面倒だし、と思っている人も多い。花を見るのは好きだが、育てるのは苦手だと思う人もいる。
花などどうでもいい、花を育てる畑や時間があるなら、野菜を育てた方が実用的だと思う人もいる。
花に対する感情は人それぞれだが、花を育てる条件さえあれば一度ぐらい育てて花を咲かせてみたいと思う人も多いと思う。花を育てる条件とは花を育てる気持ちがある、花を育てる場所がある、多少なりとも知識がある、花を育てる程度の時間の余裕がありそうだ、花には魅力がある、等々でしょう。
そこで、この寒い標津で花を育てる人のために多少の知識を参考のために書いてみたい。美しい生活環境づくりに多少なりとも参考になれば幸いです。
2花づくりのはじめに
(1)大切なことは地域の自然を知ること。
花づくりは、栽培地すなわち地域の自然条件を知ることから始まる。例えば、寒さに弱い花を寒い標津で育てようとしても無理な話で、温室とかビニールハウス等の施設の中で育てるか、家の中で鉢などで育てるなどの方法しかない。反対に、暑い地方で暑さに弱い花を育てようとしてもこれまた無理な話である。
栽培する場所の自然条件、植物の性質を知ることが大切だということである。
北海道は、春から秋までの暖かい期間が本州よりはかなり短い。まして、道東の標津は北海道の中でも暖かい期間の短いことは1、2番である。春はいつまでも霜があり、夏でも気温が30度C以上になる日など「なし」で、夜は涼しく、昼と夜との気温差も大きい。
しかし、昼と夜との気温差が大きいという自然条件は、花の色をあざやかにし、草丈は短くがっしりと育ち、病気も少なく育てやすい条件である。また、暑い地方では育て方の難しい高山植物も標津では花畑で良く育ち、いい花を咲かせてくれる。これも良いことの一つである。
また、一般的に寒さに弱いといわれている熱帯地方原産の草花も短い夏にどうにか育ち、花も咲かせてくれるものも多い。
だから、花畑で栽培することのできる花の種類も暑い地方よりは多い。特に宿根草が多く、春から秋まで次々と季節の花を咲かせることができる。気温が低いからといって花づくりの条件のすべてが悪いというわけではない。
このように、地域の花づくりは地域の自然条件と植物の性質を知るところから始まるのである。
1)土を知ろう~標津の土は火山灰の土
標津の土のほとんどは火山灰土である。火山灰土というのは、噴火で火山礫(火山灰のかたまり)や灰が積もってできた土で、一般に酸性が強く、水はけや保水力は良いが、肥料分は少なく、特にリン酸分が少ないやせた土が多い。標津の土はこんな土である。
花を育てる土は、水はけや通気性が良く、保水力があり、適当な肥料分のある土が良いわけで、土の粒の大きなぼろぼろした土が良い。粒の細かい土は、固くなって水はけや通気性も悪いので良い土ではない。粘土がこの土である。
では、標津の火山灰土はどうであろうか。肥料分の少ないやせた土であるが、その他の条件(水はけ・保水力・通気性)が良いので、植物が育つために必要な肥料分、特に堆肥(牛ふん・馬ふん・鶏ふんなどや植物の腐ったもの)のような有機質肥料と、リン酸肥料が足りないので補ってやれば良い土になる。
| 図1 草花の栽培に良い土 | |
土の粒が適当に集まっている土(粒の大きな土)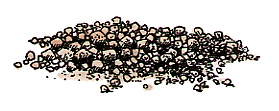 土と土との間にすきまがあって、空気や水を貯蔵していて土が固まらない。このような土は植物の根がよく出てのびる。 |
細かい粒でできた土は固まりやすい。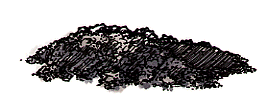 水はけが悪く、保水力が良すぎて、空気や水が通りにくい。植物の根が伸びにくい。 |
また、火山灰土は酸性が強いので石灰(炭カル等)を入れて良く耕してから栽培すれば良い。
2)植物の性質を知ろう~植物は日当たりを好むものが多い。
植物は一般的に日当たりを好むものが多い。特に、長い期間花の咲く草花は日当たりを好むものである。朝から夕方まで日が当たる場所なら問題はないが、住宅地ではそうはいかない。隣の家や大木などの陰になってしまう場所も多くなる。花づくりの計画を立てる時は、日の当たる場所を中心にしなければならない。
午前中の日当たりだと最高だが、午後からでも日当たりの良い場所は植物の育ちを良くしてくれる。半日陰(半日しか日が当たらない)や日陰でも育つ草花もあるし、常に日陰でも育つものもある。また、育ちはじめは日当たりが良く、育つにしたがって日陰になった方が良く育つ草花もある。
植物の性質を知ることも大切なことである。
3)植物の性質を知ろう~風通しも大切であるが、草花が倒れることもある。
草花を育てるには、適当な風通しも必要である。
風通しが悪いと病気になったり、害虫がついたりしやすく、草花も弱々しく育ってしまうことが多い。
しかし、風通しの良い、風当たりの強い場所だと枝や茎、花、葉が傷んでしまうことが多く、ダリア・グラジオラス・ヒマワリなどのように背が高くなる草花は、風当たりの少ない場所の方が無難である。風で倒されるからである。
日当たりが良い悪いといっても極端な場所はそう多くないので、あまり気にしなくてもよいとは思うが、草花を育てる場所を選ぶ場合に気をつけることの一つではある。
標津のように寒い地域では、風当たりの少ない日当たりの良い場所が草花を育てる場所としては良いことである。
(2)草花の種類と性質
1)草花の種類
花畑やプランター、鉢などで育てている草花をまとめて花卉類(花き類)と呼んでいる。園芸では花卉類をさらに、1~2年草、宿根草、球根類、花木類、観葉植物、多肉植物などに分けている。
家庭で多くの草花を育てているが、育てようと思う草花の性質と生い立ちを知ることが大切である。
自然の中で自然に育っている原種(野生種)。自然の中で自然に交配された自然交配種。人間が改良した園芸種などが育てられているわけである。
このような草花を育てるための注意として考えられることは、原種や自然交配種は、育っている場所の環境に合った所で育てることである。
庭や花畑で育てる場合、その庭や花畑でその草花を育てるために一番適当な場所はどこなのか。土・水はけ・肥料分・日当たり・風当たりの状態などをよく見て自然の環境条件に最も近いところを選ぶ必要がある。
野生種(自然に育っているもの)は、丈夫だが自然環境が合わないとよく育ってくれない。特に、植え替えの時や、肥料のやり方には十分な注意が大切である。自然では、植え替えや肥料をやる事はないからである。
園芸種は、人間の都合の良いように鑑賞を目的に改良されているので、土・水分・肥料・日当たり・風通し・病気・害虫などできるだけ手まめに手入れする必要がある。花がたくさん咲く草花には肥料を切らさないようにするとか、宿根草は南方系なのか北方系なのか。例えば、アスチルベは、ヒマラヤ、日本、北米などが原産地なので北方系であり、ケイトウは、インド・熱帯アジアが原産なので南方系である。
このように、原産地がどこなのかで北方系・南方系がわかる。南方系は高温を好み、北方系は寒さに強い草花である、と考えればよい。
2)一年草・二年草の育て方 その1
春に種をまいて、初夏の頃から花が咲きだし、霜が降るまで咲き続け、実がなって、寒さで枯れて一生が終わる草花を一年草という。しかし、秋に種をまく一年草(越年草ともいう)もあり、パンジー・セキチクなどがその仲間だが、寒い標津では二年草といった方がいいのかもしれない。
また、コリウス・ペチュニア・サルビアなどは、霜の降る前に花畑から鉢に植え替えて家の中におくとそのまま育ち続ける多年草の性質を持っているが、普通は一年草として育てた方がよい。
二年草は、種をまいてから二年以内に花が咲いて、実がなり一生を終える草花のことをいっている。
一般的には、秋に種をまいて次の年の春から夏、遅いものは秋に花が咲いて枯れる。寒い標津では、6~7月頃に種をまいて、秋早めに植え替えをし、雪の下で冬を越して春を待つようにする。パンジー・セキチクなどは2年草と考えて良い。
二年草は、茎や葉がある程度育ち、寒さに当たってはじめて花の咲くものが多い。ですから、春の終わり頃に種をまいて、秋早めに植え替えをして、根も充分出させて、丈夫な苗で冬の寒さに耐えるようにするのである。土ががっちり凍る標津では苗に落ち葉や枯れ草などを1~2㎝位かけて冬を越すようにすればよい。木の葉、枯れ草を厚くかけると苗が蒸れて枯れることがあるので、厚くかけない方がよい。
雪の少ない冬は凍結深度も深く、雪が早めにたくさん降れば凍結深度は浅い。ですから、雪の多い年には、苗は雪の下で安心して冬を越すので、木の葉や枯れ草はかけなくても良いが、雪はいつ・どれくらい降るかわからないので、木の葉や枯れ草で苗を守ってやると良い。
3)一年草・二年草の育て方 その2
種は良い種でないと、良い花は咲かない。良い種を手に入れる時は評判の良い信頼のおける種苗店から購入することが一番である。しかし、最近は純度の低い、粗悪な種を販売している店はほとんどないので、あまり心配しなくても良い。
その地方にあった品種を選んで育てることが大切。
標津のように寒く、霜の降らない期間(無霜期間)の短い地方では、少しでも早く育ち、少しでも早く花の咲く品種の早生種を選んで育てる方がよい。育ちも遅く、花の咲くのも遅い晩生種だとせっかく育っても花の咲く頃には霜が降って枯れてしまうことがあるからである。場合によっては、花の咲く前に霜が降って一輪の花も咲かないで枯れてしまった花畑のキクを見ることがある。花畑でキクを育てるのなら、やはり早生種の夏キクが無難でしょう。
最近、毎年のように新しい品種が販売されているが、その地方にその花が合っているかどうかをよく調べてから育てることも大切である。苦労して育てても、とうとう花を咲かせずに終わってしまったではガッカリでしょう。育つ期間は、肥料を切らさないようにすることも大切なことの一つである。
同じ場所に、同じ種類の花を何年も続けて育てないことは大切なことである。
野原で自然に育つ植物は別として、園芸種は毎年同じ土で育てると、その土を嫌う性質がある。植物によって、多少の違いはあるが、一般的に毎年とか、2~3年に一度は場所を変えて育てた方がよい。
特に
ペチュニア。
花ではないが、トマト・ジャガイモ・ナス・ピーマン・キュウリなどのナス科植物。
アスター・ジニア・キクなどのキク科植物。
ケイトウ類のヒユ科植物。
スイートピー・ルピナス、花ではないがエダマメ・アズキ・エンドウ・ダイズなどのマ メ科植物。
アサガオなどのヒルガオ科植物
などは、毎年育てる場所を変えてやるようにすると良い。
プランターの土を毎年取り替える理由も同じである。
土は水持ちの良い粒のものがよい。やせた土には堆肥を入れたり、植え替えてから肥料をやればよい。火山灰や砂の多い土の場合には、堆肥・ピートモスなどを入れて土を肥やし、水はけの悪い粘土の土には堆肥、火山灰を入れて水はけを良くすればよい。
このようにして土を良くすることを土壌改良といっている。
4)多年草の育て方
①耐寒性・半耐寒性・非耐寒性
植物には、寒さに強い耐寒性、やや寒さに強い半耐寒性、寒さに弱い非耐寒性がある。
寒い標津では、非耐寒性のものは屋外での越冬はできない。冬の寒さで枯れてしまう。
半耐寒性のものは、冬の雪の降る時期や積もる量などで凍結深度が違うので必ずとはいえないが冬を越すものは少ないと考えてよい。早く、たくさん雪が積もると土の凍結が少ないので冬を越すことができるものが多くなる。
寒性のものは、特別な気象の変化がなければ冬の寒さで枯れることはない。
②非耐寒性の草花(寒さに弱い草花)
ゼラニウム・マツバギク・ベコニア・センパフローレンス・アキランサス・ガザニア・オリヅルラン・サンスベリア・アフリカホウセンカ・カランコエ・クンシランなどで、あまり聞いたことがない花が多いようである。
屋外では冬の寒さで枯れてしまうが冬の間室内とか温室で寒さに当てないように育てれると枯れないで育つ。
③半耐寒性のもの(寒さにやや強いもの)
ガーベラ・アガサンパス・エビネ・シユンラン・シロタエギク・オモト・シュウカイドウなどであるが、寒さにやや強い。しかし雪が少なく、寒さが厳しい標津はやや寒いではなく、相当寒いので確実に枯れないで冬を越す保障はない。枯れるものが多いと考えてよい。
④耐寒性のもの(寒さに強いもの)
ポピー・アカバナムシヨケギク・アサギリソウ・アスチルバ・アマドコロ・アメリカフヨウ・アヤメ・アリウム・アルメリア・イカリソウ・ジャコウソウ・イワオウギ・イワブクロ・エゾノシモツケソウ・エゾリンドウ・エンレンソウ・オオアマドコロ・オオバナノエンレイソウ・ベンケイソウ・オダマキ・オトギリソウ・キキョウ・キク・オニゲシ・オミナエシ・キンヨウブ・ノコギリソウ・ギボウシ・クリンソウ・クレマチス・ケマンソウ・コウリンタンポポ・サクラソウ・シャクヤク・ジャーマンアイリス・スズラン・センダイハギ・タイマツソウ・デルフィニウム・ハナショウブ・ハナトラノオ・ユキノシタ・ジャガ・フクジュソウ・ホオズキ・ホタルブクロ・マーガレット・ルピナス・ルドベキアなどである。園芸種の他に野山で咲いている花の一部も入っている。このような花は、花畑に植えたままで冬を越し寒さで枯れることはない。
多年草のいいところは、一般に丈夫な種類が多いので育てるのにあまり手間がかからないことである。また、増やし方も種まき・株分けで増やせるので増やしやすい草花が多い。
このほかに、季節感がだせる・寄せ植えができるなど、いろいろいいところがある。