1 開墾の順序(伐開、入火等)
・開墾予定地面積の周囲の巾10m以上を伐開して火防線を切り火入をする。
・一度に許可になる面積は最大2ha程度
・火入の実施は風の吹かない日の午後6時から
・農家が自主的に編成する防火組合員10人以上の協力を求める。(失火に備えて)
・火入の許可書は実施前に必ず営林署から現地検査を受けて交付を受ける。
・実施日は営林署担当区員の立会を求める
・実施日を消防に通報するとともに防火組合員は交代で夜間見回りをする。
火入後の土地は
太い木(古い風倒木)、新しい風倒木、拓伐の切株、太い枝、熊笹、ブドウ、コクワ、マタタビ等のつる性のもの、稚樹の根等は島田鍬を受け付けないが、けずるようにして種を植え込む。野鳥や小動物の餌になり収穫はできない。
しかし、これをやらないと次の年荒地にもどり、開墾検定を受けられない。入植初年度は1戸当たり1ha前後の開墾検定面積しかできない
畜力作業は、入植15年で3ha程度
古多糠の場合昭和12年に入植して、昭和35年までは畜力も十分に使えず、火薬抜根・機械開墾ができるようになった昭和38年頃からようやく農業経営で生活できるようになった。1戸あたり5ha程度、子返牛1〜2頭と造材により。
図の説明
火防線は10m以上伐開
火防線の切り方
すべての可燃物を取り除く
島田鍬できれいに削る
1m以上の巾を地肌まで削り燃えそうなものを完全に取り除き延焼を防ぐ
伐開して
風倒木は両方を防火線の長さに切り片方に片付ける
笹や小枝、落ち葉等を火入の場所へ片付ける。
ゴミに火をつける
木の葉
小枝
抜根のまわりは延焼しないようにきれいに
火入の仕方
・風下と思われる地点から火を付ける
・防火線から20mくらい燃え進んだら風上と思われる地点から迎え火をつける。
・土地の中央で炎が交差して火勢の衰えを待つ
・日暮れとともに残り火が目立つようになる
・このとき夜通しで見回りを続ける
2 人力開墾に使われた道具類(機械化の現代でも農家には必要である)

・笹、小芝、ブドウつる等の刈り払いに使う
・笹刈手鎌
・山刀
・腰鋸
・伐木用中鋸
・伐木用大鋸
・伐木用窓鋸
・島田鍬
・まさかり(薪割)
・小トビ(薪)
・手オノ
3 人力用農具

・手鎌 エンバク・ソバ・イナキビ・ヒエ・アワ・トウキビ・豆類等の刈り取り
・除草ホー すべての除草作業
・窓除草ホー 除草と中耕作業等
・平鍬 野菜畑作業
・窓鍬 再墾地の手耕し、根株のまわり耕し等
・ビートタッピングナイフ ビートを抜き取り、葉と大根部分を切りはなす。
・肥料播(ラッパ)
・肥料入箱
4 伐木造材作業に使われた道具
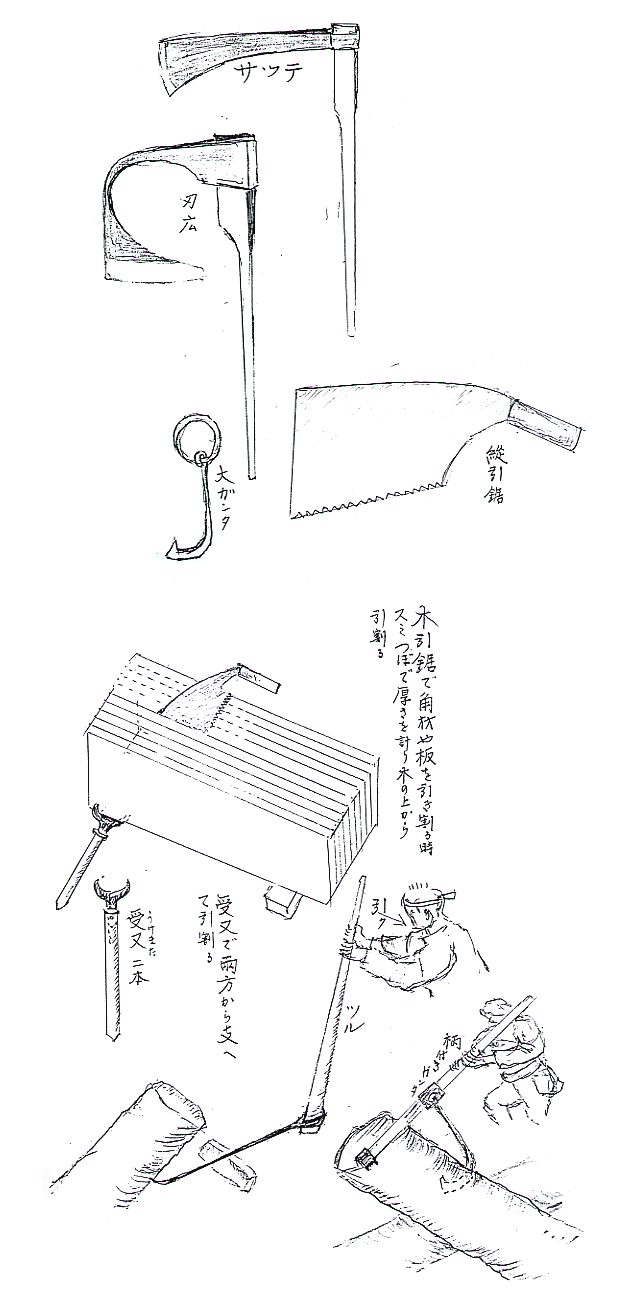
・縦引鋸
・サッテ
・刃広
・大ガンタ
・木引鋸で角材や板を引き割るとき、スミ壺で厚さを計り木の上から引き割る
・柄付ガンタ
・引く ツル
・受又で両方から支え、引き割る
・受又二本
5 伐木造材(ヤマゴ)の服装
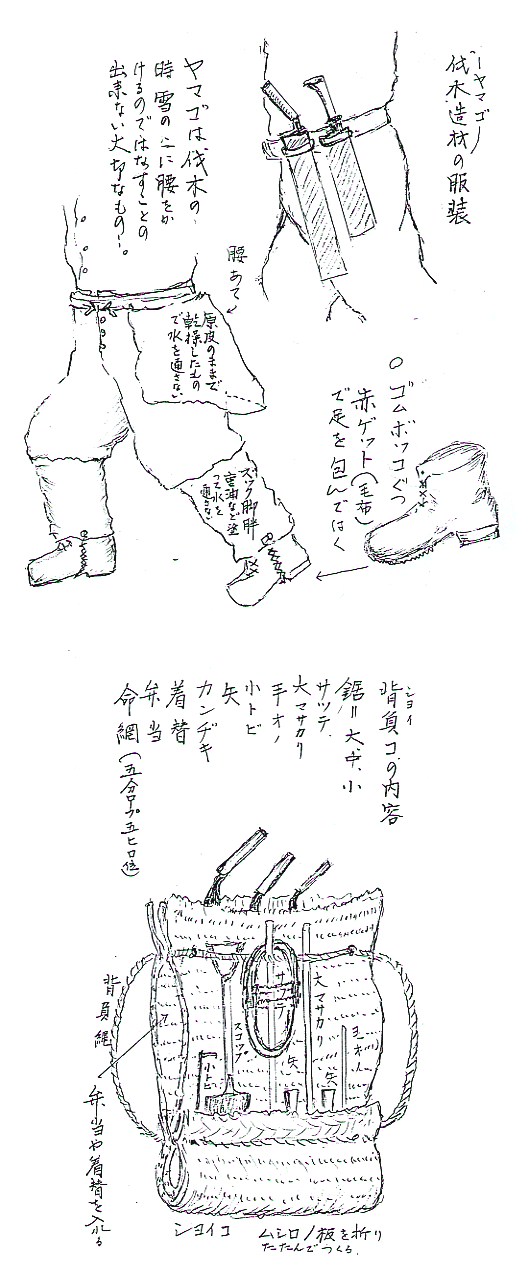
・ゴムボッコぐつ 赤ゲット(毛布)で足を包んで履く
・腰あて 原皮のままで乾燥したもの。水を通さない。
ヤマゴは伐木の時、雪の上に腰掛けるので離すことのできない大切なもの
・ズック脚絆 重油などを塗って水を通さない
・背負コの内容
鋸 大中小
サッテ
大マサカリ
手オノ
小トビ
矢
カンジキ
着替
弁当
命綱(5分ロープを7ヒロ位)
ヨオノ
矢
大マサカリ
矢
サッテ
スコップ
小トビ
弁当や着替を入れる
背負縄
ショイコ ムシロ1枚を折りたたんでつくる
6 開拓時代重宝がられたワラ工品類(昭和10年頃まで愛用された)
特に井戸掘り等には貴重品であった。
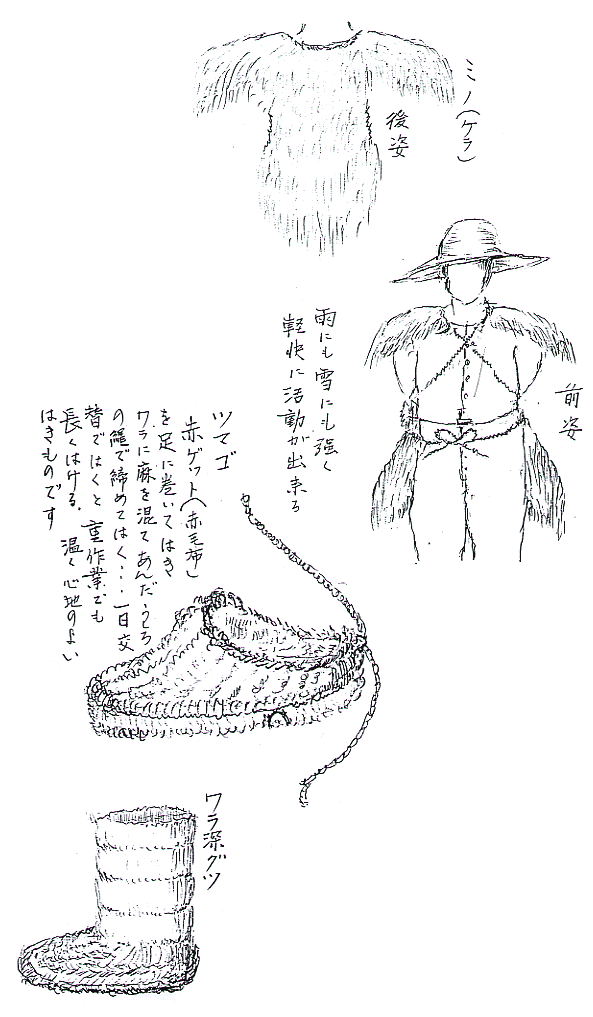
・前姿
・雨にも雪にも強く軽快に活動できる
・ミノ(ケラ)
・後姿
・ツマゴ 赤ゲット(赤毛布)を足に巻いて履き、ワラに麻を混ぜて編んだ後ろの縄で締めて履く。
一日交代で履くと重作業でも長く使用できる。暖かく、履き心地もよい。
・ワラ深グツ
7 人力農具
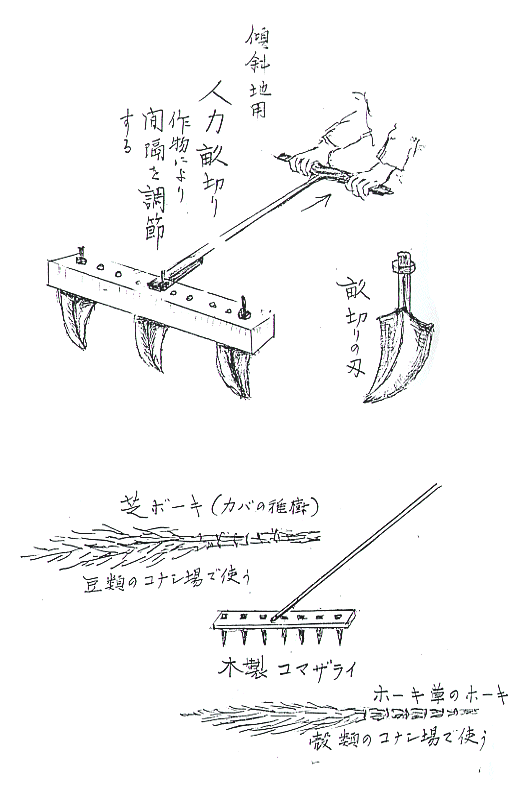
・畝切りの刃
・傾斜地用人力畝切り 作物により間隔を調節する。
・芝ボーキ(カバの稚枝) 豆類のコナシ場で使う
・木製コマザライ
・ホーキ草のホーキ 穀類のコナシ場で使う
8 人力農具

・唐竿 作物により間を広くしたり狭くしたり、編み直す
・箕
・1斗升
・斗棒
・白米1俵=4斗2升
正味 16貫300匁
俵 1貫300匁
計 17貫600匁
・1升マス
・大秤(20貫)
9 農耕馬の馬具と農器具類
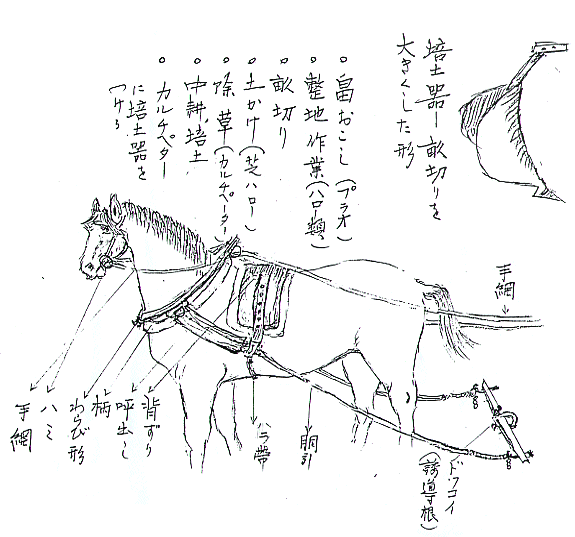
・畠おこし(プラオ)
・整地作業(ハロー類)
・畝切り
・土かけ(芝ハロー)
・除草(カルチペーター)
・中耕培土
・カルチペーターに培土器をつける
・手綱
・ドッコイ(誘導根)
・胴引
・ハラ帯
・背ずり
・呼出し
・柄
・わらび形
・ハミ
・手綱
・培土器 畝切りを大きくした形
10
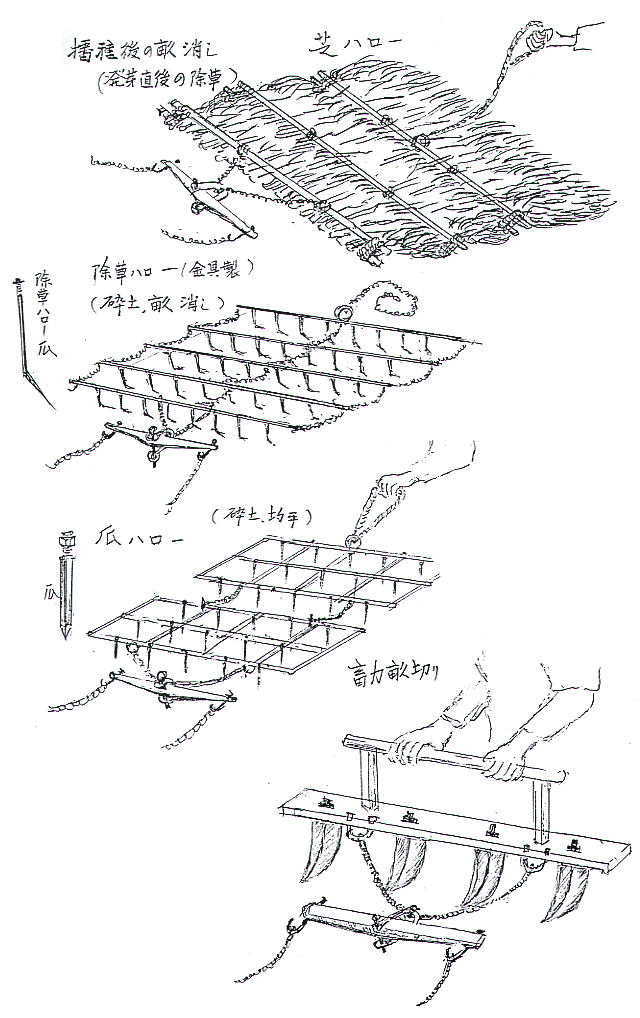
・畜力用
畜力畝切り
播種後の畝消し(発芽直後の除草)
芝ハロー
除草ハロー(金属製) 砕土、畝消し
除草ハロー爪
爪ハロー
爪
砕土、均手
11 荷馬車用馬道具
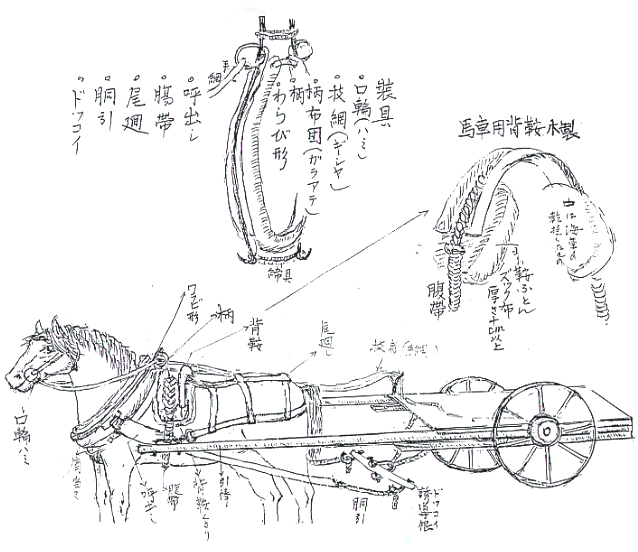
・荷馬車 金輪・輔導車(ゴムタイヤ)
馬車用背鞍木製
・中は海草を乾燥したもの
・背鞍ふとん ズック製厚さ10㎝以上
・腹帯
装具
・口輪(ハミ)
・枝綱(ギシヤ)
・柄布団(ガラアテ)
・柄
・わらび形
・手綱
・呼び出し
・腹帯
・尾廻り
・胴引
・ドッコイ
荷馬車(重輓馬)
・枝者(手綱)
・尾廻し
・背鞍
・柄
・わらび形
・誘導根(ドッコイ)
・胴引
・引棒
・背鞍くさり
・腹帯
・呼出
・肩当て
・口輪ハミ
12 大木(直径1m以上位のもの)のヤブ出し
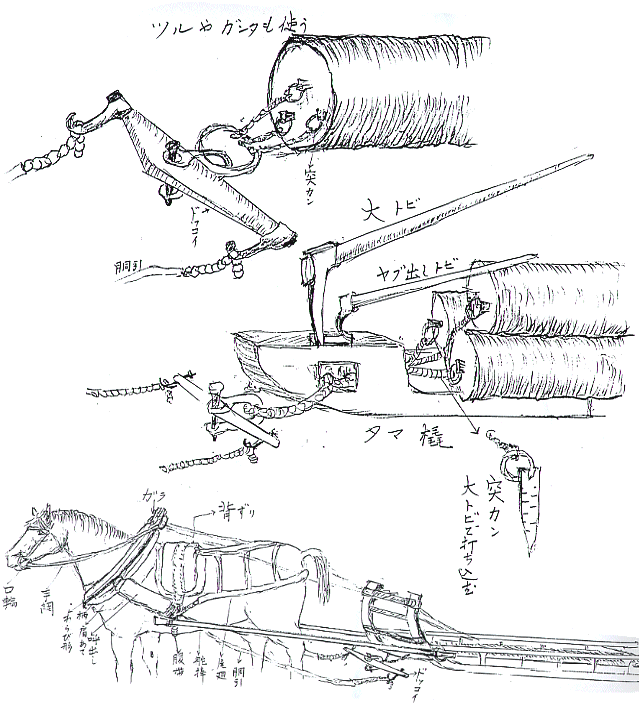
・ツルやガンタも使う
・突カン
・ドッコイ
・胴引
・大トビ
・ヤブ出しトビ
・タマ橇
・突カン 大トビで打ち込む
馬橇(中間種)
・背ずり
・ガラ
・ドッコイ
・胴引
・尾廻
・舵棒
・腹帯
・呼出し
・柄
・肩あて
・わらび形
・手綱
13 道産駒(ドサンコ)の用役
・装具の色々
・段付け鞍
・ドサンコ作業の必需品 常時着用する
・尾バサミ
・ワラと麻をまぜてつくる
・締付けなわ
・馬用わらじの拡大図
・馬わらぐつ
・ムシロを折りたたんでつくる
・締め付け縄
山奥への食糧の運搬
山奥から木炭の搬出
山地への乗り入れ、奥地の探検
ダンクラ荷物装着
・尾バサミ
・腹帯
・背負帯(皮製)
・無口
・手綱
岩石道の登り、下り蹄(ひづめ)の保護
深い雪道を歩くとき、カンジキの役を果たす。
14 燕麦落とし
おとし場はムシロ50枚位の広さです。鍬でけずって平らにしてからムシロを敷く。
この縄を両方で引っ張って反転する。
向かい合って交互に打ち下ろす
15 人力牧草収穫
・牧草鎌
・牧草三本ホーク
乾燥したら大積にして、冬牧舎に運ぶ
16 搾乳(手搾り)
・吹雪の牛乳出荷
・生産者番号
・カンジキを履いての道なき道
17 唐臼精黍(昭和10年頃使われた)
精米所のない田舎で、冬仕事としてどの農家も行っていた。
精黍、裸麦、大麦、燕麦、トウキビ脱粒等。作物によって杵の重さを変える。
凍結乾燥馬鈴薯の粉砕(澱粉作り)
肥料:大豆滓、鰊滓の粉砕
18 ひき臼の構造
大型の臼は二人でひく
用途 穀物製粉
・小麦、ソバ等の製粉
・トウキビ:挽き割って大粒のものはご飯に混ぜて炊く。粉末のものはダンゴにする。
・大豆:水に浸し、柔らかくして豆腐にする。
よく乾燥した大豆を火にかけ、イリ豆を粉にしてキナコにする。
・大麦をモヤシにし、乾燥して粉末に挽き澱粉のクズ湯を作ってこれに入れ、水飴をつくる
・ひき臼にかけた製品は目の大きさが違うフルイを使い用途別に分ける。
19
・新墾けずり播きの状況
・ビート馬鈴薯等の病害虫駆除作業
・麦、燕麦、そば、稲きび等の刈取り
・手鎌、麦刈、燕麦刈等すべての刈取りはこの鎖を使う
20 開拓者の生活
・開拓者の生活
・開拓時代の井戸
・ハネツルベ式
・ブドウやコクワのつるを使う
・ロープは凍結すると折れる
・鎖は凍結して凍傷をおこす
・井戸掘り作業は渇水期が適期である
・共同作業等により一日で掘ってしまわないと次の日は水がたまって仕事ができなくなる。深さは10m前後、井戸枠はナラ、トドマツ等水に強い木を使う。耐用年数は約20年くらい。地上付近(2mくらい)は10年程度
・井戸は年1回水替(水を底まで全部くんで捨てる)しないとどぶ臭くなるし虫も増える。
・昔の開拓者は水に不自由しない川沿いに住居をつくった。
21 歩きやすいカンジキの作り方
材料 ブドウづる、コクワづる、桑の木、キハダ等の直径3㎝くらいのもの
丸木を1時間くらい熱湯につけ、曲がるようになったら前、後の形を曲げて乾燥する。完全に乾燥したら横から引き割ると1足ができる。
丸木の中心を引き割って図のように左右に開き、雪の抵抗を防ぐ。
横から鋸で引き割る。同じ曲のものを2本作り1足となる。
細形で長いほど歩きやすく、ぬからない。